アイホール・アーカイブス
ハイバイ『ヒッキー・カンクーントルネード』
岩井秀人 インタビュー
平成27年度公共ホール演劇ネットワーク事業として、7/19(日)・20(祝)に、ハイバイ『ヒッキ―・カンクーントルネード』を上演します。「公共ホール演劇ネットワーク事業」とは、一般財団法人地域創造と複数の公共ホールが共同・連携し実施する事業です。公演に先駆け、作・演出の岩井秀人さんに、作品についてお話いただきました。
公演詳細はこちら
 岩井秀人(以下、岩井):『ヒッキ―・カンクーントルネード』は、僕が初めて書いた戯曲です。「プロレスラーになりたいけど 引きこもりの男が 外に出られない話」と大学ノートに書いた三行ほどのプロットに、16歳から20歳まで引きこもりだった自分の実体験を交えたものです。2003年にハイバイの旗揚げ作品として初演し、10年以上、再演を続けており、今回で10回目の上演を迎えます。
岩井秀人(以下、岩井):『ヒッキ―・カンクーントルネード』は、僕が初めて書いた戯曲です。「プロレスラーになりたいけど 引きこもりの男が 外に出られない話」と大学ノートに書いた三行ほどのプロットに、16歳から20歳まで引きこもりだった自分の実体験を交えたものです。2003年にハイバイの旗揚げ作品として初演し、10年以上、再演を続けており、今回で10回目の上演を迎えます。
引きこもりだった頃、「リングス」という総合格闘技をテレビでよく見ていたんですが、プロレスラーの前田日明が対戦相手のディック・フライにひどい目に遭わされていたのがどうしても許せず、深夜に近所の公園へ行き、通信販売で買ったサンドバックを木に縛り付けて蹴るということをやってました。プロレスは相手と息を合わせるという、コミュニケーション能力がとても必要な競技なんですが、そのプロレスラーに憧れていた僕は、家に引きこもり、郵便屋さん相手にも挙動不審になってしまうほど臆病だったんです。その理想と現実の開き具合が、自分にとって“悲劇”でもあるし“喜劇”でもあると感じて、当時のことを思い出しながら書きました。
あと、岩松了さんの舞台に1ヶ月近く関わったことで、「しゃべり言葉の演劇」を知れたこともきっかけです。それまで僕が大学で教わってきた演劇は、文語体の戯曲で、登場人物の会話にこそ意味があり、そのために俳優は仰々しくてかっこいい台詞を発するというもので、卒業する頃にはそういう演劇に嫌気がさしてまして…。そんなときに出会った岩松さんの舞台は、登場人物の会話ではなく、その様子を黙って見ている人物にスポットを当てている、つまり、メインとなる大きな流れがある横で、そこに関われないでいる人物やその人たちの疎外感を描いている気がして、自分にとって価値のある演劇だと思えたんです。 今でも僕は、自分が観客ならば、人生で上手くいかない場面でどういう行動が取れるか、どういう耐え方があるのかを描いた作品に価値があると思うし、観たいと思っています。
今でも僕は、自分が観客ならば、人生で上手くいかない場面でどういう行動が取れるか、どういう耐え方があるのかを描いた作品に価値があると思うし、観たいと思っています。
まあ、当時はそこまで深く考えておらず、岩松さんのような“しゃべり言葉”で台本を書いていいんだという、その自由度に大興奮して、一人でゲラゲラ笑いながら大学ノートに台詞を書き、三日間ほどで仕上げました。興味が赴くまま書きましたから、改めて読み直すと原始人が書いたみたいだと思う(笑)。でも、自分の体験や身近な人たちの現実に起きた出来事を描くという、僕の戯曲のすべてに通じる“原点”になった作品です。
――ハイバイでいちばん多く再演されている作品ですよね。
岩井:再演が多いこの公演スタイルは珍しいとよく言われます。でも、僕は新作を次々とつくるより、せっかく面白い作品ができたのだから、まだ観てもらっていない人たちに観てもらえる活動をしたほうが良いと思っています。すごく面白い作品なら、再演するときに「またやってくれるんだ!」とお客さんが知人を連れてきてくれる。僕はそういったことをもっと狙ってやっていかなければと思っています。
この作品は、何度再演しても動員を減らすことなく続けられていて、僕もすごく自信のある作品です。なので、初めてハイバイが東京以外の地域で上演するときも、韓国で上演するときも、選んだのはこの作品でした。東京郊外の50人程度の小さな劇場で初演した作品が、再演を続けることで、今回は全国10都市で上演するなど、どんどん広がりをみせていることが面白いです。
――韓国で上演してみていかがでしたか。
岩井:韓国での上演当時、向こうにはまだ「引きこもり」という概念がなかったのですが、お客さんは爆笑してくれましたし、感動してくれました。ところが、ここ1~2年くらいで急激にその問題が出てきているそうです。それで、韓国の方に「もし、自分の息子が家の外に出ず、経済活動もせず、学校にも行かなかったら、どうしますか?」と質問したら、「その情報を家の外に漏らさないようにする」と答えたんです。それって別のいろんな問題が生まれる可能性があって恐ろしいと感じました。日本では、今や、引きこもりのことを「自宅警備」と言い換えて、生き方のひとつと受け入れようとしていたり、会話で「先週、家に引きこもってたんだよね」なんて軽く使われたりするほど、その概念が浸透していってますよね。なんだか改めて、日本って面白い国だなと思うきっかけになりました。
――前回の再演で、新しい発見があったそうですね。

岩井:この作品は、台本をほとんど変えずに、初演に近い状態で再演を続けていたんです。ただ、今年2月に参加したTPAM(国際舞台ミーティング)での上演で、演出方針を変えました。TPAMには多くの海外のお客さんがやってくるのですが、「引きこもり」という概念が日本ほど浸透していない海外の人には、この作品の本来の面白さが伝わりにくいのではないか…と感じたんです。引きこもりの実態を誇張して見せるよりも、まず「引きこもりとはどういう人か」というベースを見せる必要がある。それで演出をシフトチェンジしました。それまでは、「どれだけ(観客を)笑わせることができるか」をいちばんに考えていて、「ここでも笑いが取れる」「あそこでも笑いが取れる」といろいろ詰め込みすぎていたんですが、それを整理してシンプルにしました。その結果、「人は寂しいんだ」という作品の本質的なテーマが浮き彫りになったんです。もちろん、笑えない話になったわけではありません。この作品で何を最低限伝えなければいけないかに立ち戻っただけです。
――今までと作品が大きく変わるのですか?
岩井:雰囲気が少し違う程度だと思います。演出を変えたことで、作品に余白ができて、良い意味で、お客さんに考えてもらう時間や、選択してもらう余地が増えました。作品としてもより豊かになったと思います。今まで、演出で作品は変わらないと思っていたんですけど、微妙なニュアンスは変えることができるんですね。普段、台本を書きながら演出をすると、書いたイメージを立ち上げることしか考えていなくて…。それが、演出次第で作品がこんなにも新鮮になるんだと、自分でもびっくりしています。僕は、お客さんには、演劇を観ながら自分のことについて考える時間を持ってほしいと思っているので、僕の目指している方向性の表現に戻すことができたんじゃないかなと思います。だから、今回もこの方向性をベースに作っていこうと思っています。
――演出家として、客観的に作品に向き合ったとき、改めて何を伝えたいですか。
 岩井:「生きていくことの困難さ」ですね。ただ、これは僕の作品の全部に通じていることで、より多くの人と共有したいから、手を変え、品を変え、いろんな作品に反映させているんですけれど(笑)。僕がお客さんからの反応でいちばん嬉しいのは、「うちにもこういう人がいて」「私もそういう時期があって」と、いきなり自分のことを話し出してくれたときです。作品と自分とを重ね合わせながら僕の作品を観てほしいと思っているからです。『ヒッキー・カンクーントルネード』は、特に僕にとって嬉しい反応が多かった作品です。たぶん、コミュニケーションの難しさ、「自分が他者の中でどう生きていくか」について、問題提起しているからでしょうね。実は、自分で書いたものなのに、すごく長い時間をかけて解読し続けている気がしています。だから何度も再演を重ねているのかもしれません。
岩井:「生きていくことの困難さ」ですね。ただ、これは僕の作品の全部に通じていることで、より多くの人と共有したいから、手を変え、品を変え、いろんな作品に反映させているんですけれど(笑)。僕がお客さんからの反応でいちばん嬉しいのは、「うちにもこういう人がいて」「私もそういう時期があって」と、いきなり自分のことを話し出してくれたときです。作品と自分とを重ね合わせながら僕の作品を観てほしいと思っているからです。『ヒッキー・カンクーントルネード』は、特に僕にとって嬉しい反応が多かった作品です。たぶん、コミュニケーションの難しさ、「自分が他者の中でどう生きていくか」について、問題提起しているからでしょうね。実は、自分で書いたものなのに、すごく長い時間をかけて解読し続けている気がしています。だから何度も再演を重ねているのかもしれません。
――同名の小説を出版(※)されていますが、小説を書いたことで異なる見方は生まれましたか。
岩井:小説は書いても書いても一人なので、本当に辛かったです。けれど、登美男が電車で乗客にボコボコにされるシーンとか、舞台で描けなかった部分は思う存分書けました。小説を書いてみて「小説にしかできないこと」をすごく感じることができました。この経験を活かし、稽古のときは、身体性を重視するなど「演劇にしかできないこと」をより意識的にしようと思っています。
※『ヒッキ―・カンクーントルネード』(河出書房新社 2014年刊)
――この作品には、「高校演劇」のための台本があるそうですね。
 岩井:高校演劇の大会で審査員を務めたことがあるんですが、高校演劇って、時間や人数の制約があるから、好きな台本を選べないんですよね。部員数に合わせなきゃいけないから、面白くなりえないような台本を選ぶしかなかったり、演劇の知識に乏しい先生が台本にとんでもない手の入れ方をしたり…。不幸な状況にあると感じたんです。僕の台本は基本的にほとんど上演許可を出していないんですが、「ダメ」なんて言っている場合じゃないと。それで、90分ある『ヒッキー・カンクーントルネード』を一所懸命削って、上演時間60分の高校演劇用の台本をつくりました。でも印象は通常版とほとんど変わらないんですよ。どうしてなのか僕も不思議なんですが(笑)。あと、高校生という時期に、普通のお芝居をしてほしいという気持ちもあります。主人公は「16歳で引きこもりをはじめて10年近く経ってしまった」という設定なので、演劇を通して、引きこもりを取り巻く家族の立場をほんの少しでも疑似体験してほしいとも思っています。
岩井:高校演劇の大会で審査員を務めたことがあるんですが、高校演劇って、時間や人数の制約があるから、好きな台本を選べないんですよね。部員数に合わせなきゃいけないから、面白くなりえないような台本を選ぶしかなかったり、演劇の知識に乏しい先生が台本にとんでもない手の入れ方をしたり…。不幸な状況にあると感じたんです。僕の台本は基本的にほとんど上演許可を出していないんですが、「ダメ」なんて言っている場合じゃないと。それで、90分ある『ヒッキー・カンクーントルネード』を一所懸命削って、上演時間60分の高校演劇用の台本をつくりました。でも印象は通常版とほとんど変わらないんですよ。どうしてなのか僕も不思議なんですが(笑)。あと、高校生という時期に、普通のお芝居をしてほしいという気持ちもあります。主人公は「16歳で引きこもりをはじめて10年近く経ってしまった」という設定なので、演劇を通して、引きこもりを取り巻く家族の立場をほんの少しでも疑似体験してほしいとも思っています。
――出演者についてはいかがですか。
岩井:今回は、引きこもりの主人公・登美男を田村健太郎が演じます。この役は、今まで僕や元劇団員が演じていたんですが、毎回すごく苦労していました。僕がこの役に思い入れが強すぎるためか、本番中の袖で俳優を捕まえて怒鳴ったり…まあ色々ありました。けど、田村君が入ったことで、とても磐石になりました。反射神経の良さとかクレバーに動ける身体性とかはもちろんですが、彼は恐怖や驚きを自分の内側で起こすことができる俳優なんです。それができる俳優は意外と少なくて…。若いけど素晴らしい俳優です。出張お姉さん役のチャン・リーメイは初演からずっと同じ役をお願いしていますし、平原テツはお母さん役をやり続けてもう10年近くになるかと思います。あと、出張お兄さん役の後藤剛範は、色黒でめちゃマッチョなのに、ビジュアルと正反対の気質を持っている俳優です。彼の中にちっちゃい女の子が入っていて、彼を操作しているんじゃないかなと思うぐらい(笑)。個人的には「いい俳優を発掘したぞ」と思っていて、皆さんにはウハウハしながら観てもらえると思っています。
(2015年6月 大阪市内にて)
平成27年度公共ホール演劇ネットワーク事業
ハイバイ『ヒッキー・カンクーントルネード』
作:演出/岩井秀人
2015年7月19日(日) 19:00
20日(月・祝)14:00
18:00
詳細はこちら
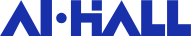




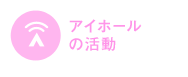


![[予約受付中]
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
令和7年度もやります!
\焼酎亭AI・HALL寄席/
関西小劇場で活躍する俳優を中心に結成された「焼酎亭一門」。
アイホールのイベントホール ホワイエに高座を設置し、カジュアルな落語会を2021年から開催しています。
役者ならではの落語。
古今東西の名曲を奏でるお囃子隊の演奏。
にぎやかで楽しいアイホール寄席へ、ぜひお気軽にお越しください
アイホール寄席初出演の方もいらっしゃいますよ~
出演者など詳細はアイホールWEBサイトまで(@ai_hall)
https://www.aihall.com/aihallyose_koi0531/
=====
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
料金:1,000円(全席自由)
※配信チケットもございます!
[予約方法]
※いずれも当日のご精算となります。
▼予約フォーム
https://torioki.confetti-web.com/form/3952/12718
▼アイホール
TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)
MAIL:info@aihall.com
=====
#焼酎亭 #アイホール寄席 #鯉 #寄席 #落語会 #落語 #役者落語 #演劇 #芝居 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
