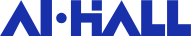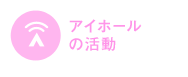アイホール・アーカイブス
令和2年度「現代演劇レトロスペクティヴ」演出家対談 松本修×小原延之

アイホールでは今年も現代演劇レトロスペクティヴを開催します。令和2年度はMODEの松本修さんの演出で柳美里さんの『魚の祭』を、小原延之+T-works共同プロデュースとして小原延之さん作・演出で『丈夫な教室』を、それぞれ上演します。演出家のお二人に当館ディレクターの岩崎正裕がお話しを伺いました。
★『魚の祭』について
岩崎:例年、現代演劇レトロスペクティヴは、新しい演出家が過去の作品に取り組むことでその作品の魅力を発見するという趣旨でしたが、今年は初演を手がけた演出家による「リ・クリエイション」の色彩が強くなっています。まず、お二人に初演を立ち上げられたときのお話をお聞かせいただけますか。
 松本:1992年が初演、翌年再演なので、今回が約27年ぶりの上演です。柳美里さんとの出会いは、知り合いの演劇評論家の方から「柳美里という面白い作家がいるから会ってみないか」と言われたのが最初です。その後、お互いの公演を観に行ったりして交流が始まり、青山円形劇場のフェスティバルでMODE×青春五月党として組んで公演をすることになりました。このとき、僕から「いま関心あるもの、好きなものを書いてください」とお伝えし、出来あがったのが『魚の祭』です。読んだときの第一印象は、「きつい内容をそこまで書くのか?」という戸惑いと、がっつり書き込まれた台詞量の多さでした。
松本:1992年が初演、翌年再演なので、今回が約27年ぶりの上演です。柳美里さんとの出会いは、知り合いの演劇評論家の方から「柳美里という面白い作家がいるから会ってみないか」と言われたのが最初です。その後、お互いの公演を観に行ったりして交流が始まり、青山円形劇場のフェスティバルでMODE×青春五月党として組んで公演をすることになりました。このとき、僕から「いま関心あるもの、好きなものを書いてください」とお伝えし、出来あがったのが『魚の祭』です。読んだときの第一印象は、「きつい内容をそこまで書くのか?」という戸惑いと、がっつり書き込まれた台詞量の多さでした。
それまでの僕は、チェーホフの戯曲を解体して再構成するという作業をやっていまして、チェーホフですら説明台詞が多いと感じて台詞をばっさばっさカットしたり、ゴダールやトリュフォーの映画に出てくる似たシチュエーションに置き換えたりしていました。俳優たちも一緒にその作業をやっていたから、「(『魚の祭』の)この台詞はこの状況で言わないんじゃない?」なんて意見が出たり。「よし、現場でつくるぞ」と戯曲の台詞やト書きをバサッと削ったり戯曲に手を入れたりしていました。ただ彼女には必ず稽古場に立ち会ってもらった。「君の書いたのと、手を入れてアレンジしたのと、どっちがいい?」と稽古を見せながら進めていたんです。俳優たちも2パターンの台詞を覚えて演じてくれて。だから、上演台本と出版されている『魚の祭』とは少しタッチの違うものになっています。
岩崎:当時、柳美里さんは23歳ですよね? そういうとき、稽古場は紛糾しそうですけど、その辺は円満に上演にこぎつけられたんですか?
松本:紛糾はしなかったけど、ムスっとはしていたね。「そこはやめてほしい」という意見も言ってくれたけど、通し稽古やゲネプロ観て、最終的には「いい」と言ってくれた。でも、やっぱり悔しい思いはあったと思いますよ。
岩崎:書いたものをざっくり切られるっていうのは、作家としては身を切られる思いですよね。
小原:現場にしっかり立ち会わせて、その場でちゃんとディスカッションして了承を得るのはすごく誠意のあるやり方だと思います。
松本:今回は、柳美里が書いたことを尊重したいと思い、初演再演で僕がカットした台詞を復活させ、書き直したところをカットするという作業をしています。初演の俳優は経験のある人ばかりで、作家が書いた台詞を一言一句喋らなくても戯曲に書いてあることを伝えることができる技術を持っていました。でも今回は20代前半の俳優たちが多く、柳美里の文体が持つ、ちょっと引っかかりのあるザラっとした、あるいはザワッとさせる言葉が、つるつると上滑りしてしまう。逆にカットした台詞を復活させて、それを言わせることで観客や相手役に引っかかるシーンになるんですよ。だから今回は、柳美里が約30年前に書いた戯曲に近いかたちで上演しようと思います。そのことで、彼女がなぜそう書きたかったのかがみえてくると思っています。
★『丈夫な教室』について
岩崎:初演当時、附属池田小事件を取り上げることに対する、劇団内の反応はどうだったんですか?
 小原:若い俳優たちは特にポカンとしてましたね。もともと「そとばこまち」は、学生劇団のノリを継承しつつ関西のエンターテインメントを引っ張っていた劇団です。辰巳琢郎さんから上海太郎さん、生瀬勝久さんと受け継がれた座長を私が継承して以降も、それなりに観客を楽しませる作品を作ってました。やっぱりそういう作品はお客さんの反応が良いんですね。ただ僕自身は、思っているのと何か違うと内に秘めるものを持っていました。当時34歳でしたが、もう少し社会に働きかける作品に取り組んだ方がいいんじゃないかと提案し、それに理解を示してくれた劇団員たちとミーティングを重ねてこの作品を作りました。作・演出として劇団を引っ張ってきて、ようやく手ごたえを感じたことを覚えています。ただ、上演成果として周りから得た評価より、劇団内評価はすごく低かったのを覚えています。
小原:若い俳優たちは特にポカンとしてましたね。もともと「そとばこまち」は、学生劇団のノリを継承しつつ関西のエンターテインメントを引っ張っていた劇団です。辰巳琢郎さんから上海太郎さん、生瀬勝久さんと受け継がれた座長を私が継承して以降も、それなりに観客を楽しませる作品を作ってました。やっぱりそういう作品はお客さんの反応が良いんですね。ただ僕自身は、思っているのと何か違うと内に秘めるものを持っていました。当時34歳でしたが、もう少し社会に働きかける作品に取り組んだ方がいいんじゃないかと提案し、それに理解を示してくれた劇団員たちとミーティングを重ねてこの作品を作りました。作・演出として劇団を引っ張ってきて、ようやく手ごたえを感じたことを覚えています。ただ、上演成果として周りから得た評価より、劇団内評価はすごく低かったのを覚えています。
岩崎:これがきっかけで小原さんは小原さんの道を歩み始めるわけですよね。
小原:結果、そうなりましたね。
岩崎:社会的な題材を扱っていく路線になったきっかけは何だったと思われますか?
小原:実は社会的な主張があって「附属池田小事件」を取り扱ったわけではありません。最初は、酒鬼薔薇事件の加害者が保釈になったことでした。加害者が社会的に更生したと認められて出所したとき被害者はどういう夜を過ごすのだろうか、という被害者と加害者の関係性を考えてみるところから書き始め、書き進めていくうえでどんどん池田小事件の方向を向き始めたんです。だから、初演のときは「附属池田小事件をモチーフに」とは謳っていませんでした。あとは、出演者の人数が多く、暗転すると大変だから、ワンシチュエーションにしようという作り方をした覚えもあります。そういった演出プランに関しても、エンターテインメントではなく、よりストレート・プレイと呼べるものになっていった気がします。一つの教室の中で、出来事が積み重なっていき一つの事件を事象として出現されるプランです。これは事件現場を観客も経験していただくくらいシリアスにしようと思いました。今、改めて作っていて気づいたのですが、この事件の再現というのは裏を返せば被害者を見世物にするエンターテインメントじゃないかと。この点は良くも悪くも劇団そとばこまちの魅せる感覚だったのかと思います。今はこの感覚は持ち合わせてないのですが、出演者には被害者に寄り添う作品としてどのようにモラルを持って演じてもらうかをテーマにしてもらっています。
★演技論にたどり着くまで
 岩崎:松本さんはもともと文学座に在籍されていましたよね。文学座らしい抑揚のきいた台詞術から、台詞を極限まで絞り込む手法へと移り変わったきっかけはあったんですか?
岩崎:松本さんはもともと文学座に在籍されていましたよね。文学座らしい抑揚のきいた台詞術から、台詞を極限まで絞り込む手法へと移り変わったきっかけはあったんですか?
松本:文学座のチェーホフは寝てしまうけど鈴木忠志のチェーホフは面白い、この違いはなんだ、が最初です。鈴木忠志のチェーホフは台詞量は10分の1だし、ラネーフスカヤは握り飯食べて演歌を歌うし、「こういうやり方もありなんだ」と思ったんですよね。100年前に書かれた戯曲だけど、チェーホフがやろうとしていたことは今にも通じることだと思いますね。例えば『かもめ』の四幕、ポリーナがトレープレフにマーシャのことを優しくしてあげてくれというシーンで、トレープレフは一言も発さずにそのままスッと出て行く。そういう演出の手法をすでに書き込んでいるわけです。
岩崎:ああいう度胸のいること、作家はなかなかできないですよ。松本さんたちは革新性を演劇に求めてきたと思うんです。僕ら1980年代に演劇を始めた者から見ると、文学座はガチガチの保守的な新劇のように見えていたわけですけど、そこから松本さんたちが出てきて、また何か新しいことが始まるんだという感覚がありましたね。
松本:僕は学生劇団でアングラ劇みたいのをやってまして、そのあと25歳の頃に文学座に入ったんです。だから入団当初は新劇のシステムがとても新鮮でした。いわゆるナチュラルに見える演技の方法があって、「この距離でいるんだから、そんな大きい声出さなくていい」とか「わざわざ腰落として、大きい声で話す人はいないから」と指摘される。リアリズム、ナチュラリズムだけど、世の中にいる人の形を使ってやりましょうという発想はやっぱりとても面白かった。ただ、杉村春子や太地喜和子は、リアリズムがベースなのに、その域を越えた演技をしている。芝居の見せ方が、ある意味歌舞伎的とか状況劇場にも通じるところもあって、それはお芝居だからできることだと思いました。リアリズムから浮いちゃうところまでやっちゃうんです。それが本当に面白かったですね。
岩崎:小原さんはそとばこまちに入ったきっかけは何だったんですか?
小原:面白そうだったからですね(笑)。大阪に出てきて、それこそ養成所に入って新劇をやっていけば、いつかは面白くなるだろうと思ってたんですけど、全然そうじゃなくて。それで劇団そとばこまちのオーディションに応募したんです。そこで、今、面白いと思ったことをそのまま舞台にしてもいいという発見があり、エンターテインメントの路線に行ったんですよね。ただ、どうしたら生瀬勝久さんや山西惇さんのような芝居ができるかはわからずじまいでしたね。
岩崎:あのお二人は芝居が嘘をついてないんですよ。今、ドラマの世界で評価されているのはリアリズムの素地があったからでしょうし、二人ともエンターテイナーでしたね。そう考えると、方法論としては、そとばこまちはリアリズム寄りだったのかもしれません。だからこそ、小原座長の体制で、この『丈夫な教室』が生まれたとも言えるかもしれないですね。
★リ・クリエーションに向けて
岩崎:最後に、リ・クリエーションにあたり、新しい俳優たちの作業も含めてどんなものが見えてきてるかお聞かせください。
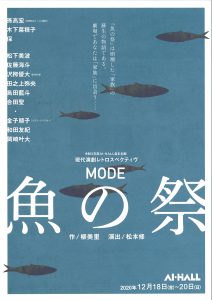 松本:今回、40~50代以上のベテラン俳優と近畿大学の学生たちとの演技に明らかに差があって。学生たちは、ナチュラリズムをベースにした演技をするんですけど、台詞がつるつる滑っていくのね。戯曲のシチュエーションをどう自分の中で実感して、どう表現するか、演技基礎実習みたいなのを毎日やってる感じですね。とにかく若い子は台詞のテンポが速くて、上演時間が半分になるんじゃないかというくらい。だけどそれじゃ全然伝わらないから、「音を上げて」とか「台詞喋る前に相手をじーっと睨んでから」とか、そういうことを毎日稽古場でやってます。若い世代に今とは違う演技のスタイルを経験させているのは面白い。柳美里は特殊な育ちをした劇作家ではあるけれども、それでもやっぱり『魚の祭』は時代を反映した戯曲だと思いますね。当時は、平田オリザ的な演劇も出始めたころだけど、青年団の演技では成立しない世界を書いてるから。だからこそ、若い世代と一緒にチャレンジできる今の現場はすごく楽しいですね。
松本:今回、40~50代以上のベテラン俳優と近畿大学の学生たちとの演技に明らかに差があって。学生たちは、ナチュラリズムをベースにした演技をするんですけど、台詞がつるつる滑っていくのね。戯曲のシチュエーションをどう自分の中で実感して、どう表現するか、演技基礎実習みたいなのを毎日やってる感じですね。とにかく若い子は台詞のテンポが速くて、上演時間が半分になるんじゃないかというくらい。だけどそれじゃ全然伝わらないから、「音を上げて」とか「台詞喋る前に相手をじーっと睨んでから」とか、そういうことを毎日稽古場でやってます。若い世代に今とは違う演技のスタイルを経験させているのは面白い。柳美里は特殊な育ちをした劇作家ではあるけれども、それでもやっぱり『魚の祭』は時代を反映した戯曲だと思いますね。当時は、平田オリザ的な演劇も出始めたころだけど、青年団の演技では成立しない世界を書いてるから。だからこそ、若い世代と一緒にチャレンジできる今の現場はすごく楽しいですね。
岩崎:『魚の祭』を読み返しましたけど、いささかも古びてないですね。携帯ではなく留守電だったりと時代は変わってますが、人と人との間で起こってることは今と何も違わないと思いました。
小原さんは、本番直前の稽古まで台本を直されますよね。『丈夫な教室』のときも、その作業はされていたんですか?
 小原:本番2週間前にホンが完成して、3日前くらいまで微調整してました。俳優のなかには 「この台詞はこう言ってくれ」と伝えたのみで舞台に出てくれた人もいました。この方法は「そとばこまち」という場があったからこそできたと今は思います。フリーになって同じことをやっても、それではダメだと思い知らされました。
小原:本番2週間前にホンが完成して、3日前くらいまで微調整してました。俳優のなかには 「この台詞はこう言ってくれ」と伝えたのみで舞台に出てくれた人もいました。この方法は「そとばこまち」という場があったからこそできたと今は思います。フリーになって同じことをやっても、それではダメだと思い知らされました。
今回のキャスティングは、共同プロデュースで組んでいるT-worksの松井さんと一緒にしました。だから初めて手を組む俳優が非常に多く、かつフィールドが違うエンターテインメント系の人たちが参加してくださったので、良い化学反応があればと思っています。台本は改めて読み返すと、台詞は本当にエンターテインメント系だと思いました。当時と今は、考え方や見せ方は大きくは変わっていないはずなんですけど、やはり当時は言葉のこだわりはあまり無かったんだと気付きました。やっぱり今とはかけ離れていて、そこをどうしていくかがひとつの課題です。言葉の選び方を一言一言精査して、オーバーホールみたいなことをしようと思ってます。その時にいろんないらない部品がでてくると思いますが、その点は、過去の自分に敬意を払って、ばらしていこうかと思っています。
岩崎:俳優陣はみんな芝居ができる人たちですよね。俳優同士の関係の作り方で面白いことができそうで、見え方が変わるんだろうなと思います。
(2020年11月大阪市内)
■令和2年度「現代演劇レトロスペクティヴ」
MODE『魚の祭』
2020年12月18日(金)~20日(日) 公演詳細
小原延之+T-works共同プロデュース
『丈夫な教室-彼女はいかにしてハサミ男からランドセルを奪い返すことができるか-』
2021年1月14日(木)~17(日) 公演詳細