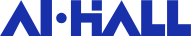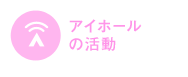アイホール・アーカイブス
鼎談 はしぐちしん×横山拓也×山口茜 (前編)
アイホールでは今秋、関西の3つの中堅劇団が初登場します。劇団で中心的な役割を担う3名にお集まりいただき、ディレクターの岩崎正裕と作品のことを中心にお話いただきました。
■コンブリ団『ブラックホールのそこ』 10月2日(金)~4日(日)
 岩崎:はしぐちさんはもうベテランですし、俳優として何度もアイホールの舞台にお立ちになっていますよね。
岩崎:はしぐちさんはもうベテランですし、俳優として何度もアイホールの舞台にお立ちになっていますよね。
はしぐち:僕が初めてアイホールに立ったのは、1995年の阪神大震災後の『カラカラ』(桃園会)初演に出演したときです。そのあとも俳優として燐光群や桃園会などで何度か舞台に立っていますが、コンブリ団としてはやるのは初めてです。いつも小さい劇場でやっていたので、アイホールで上演することに今まで現実味がなかったんです。でもアイホールでやるなら、劇場の高さを使った演出をやりたいと思いまして、それで、ビルの谷間につくられているパブリックスペースというか公園ですね、それを舞台に、三方にベンチがあって、そこで同時進行する3つの話が絡み合うという作品にしました。また、今作は、僕が評価された作風とは少し違う手法をとっています。
岩崎:具体的にいいますと?
はしぐち:今までは引用で作品を創ることが多かったんです。『ムイカ』(第17回OMS戯曲賞受賞作)でしたら、原爆の投下シーンを時系列で俳優に語らせることで立ち上げたように。登場人物の表記も男1、女2と記号化していましたが、今回は、一人の役者が一役を担う会話劇にしました。
岩崎:コンブリ団は、はしぐちさんを中心に、作品のたびに人を集めるという集団性ですが、今回の座組みはいかがですか?
はしぐち:面白いです。今までは女性の多い座組みでしたが、今回は燐光群で共演した橋本浩明くんや、第七劇場の小菅紘史さんという男性が加わることで、ぐっと広がりを持ちましたし、すごく刺激を受けています。あと、佐々木花奈子という若い俳優も加わっています。この子はもともと三重の高校演劇出身者で、僕が県大会の審査員をしたときに出会ったのですが、卒業後も演劇を続けていて、去年、アイホールの演劇ラボラトリーにも参加しています。彼女がいることで、二世代の年齢幅があるキャスティングが可能になって、母娘の物語を現実的なリアリティを持った関係性で見せることができるのはありがたいです。
■トリコ・A『つきのないよる』 10月30日(金)~11月2日(月)
 岩崎:今回は再演ですが、初演とは全く違うんですよね。その経緯からお聞かせいただけますか?
岩崎:今回は再演ですが、初演とは全く違うんですよね。その経緯からお聞かせいただけますか?
山口:初演が終わったあと、自分が書きたかったところまで到達できていないと気づきまして、それで「もう一度やりたい」と思いました。あと、この作品の前までと、以降からではお客さんのリアクションが全く違うんです。それまでは、「わけが判らない」とか「パッションだけ」と言われることが多かったんですが、今まで以上に外向きな感じで書いたんです。するとお客さんが楽しんでくれた。もちろん俳優の力が大きかったんですが、今回は、この楽しんでいただける要素を兼ね備えたうえで、自分のやりたいことを実現したいと思っています。
岩崎:現実にあった木嶋佳苗の事件(通称:首都圏連続不審死事件)を題材にしているんですよね。具体的に前作とどういう部分が変わるんですか?
山口:ストーリーが全く違います。書きたいことは何も変わってないんですが、それを表現するための枠を変えているというか、お客さんと共有するための手段を変えています。台詞も場所も役柄も何もかも変わります。
岩崎:くるみざわしんさんがドラマドクターとして名を連ねていらっしゃいますが、どんな作業をされているんですか?
山口:彼は劇作家でありながら、本職は精神科医でもいらっしゃって、境界性人格障害を専門とされています。20代の頃を振り返ると、もしかしたら私自身が境界性人格障害だったのでは、と思っていて…。30代になると治るらしいのですが、今となっては、なんであんな言動だったのか、なんであんなに生きづらかったのか、自分でもよく判らないんです。台本を書く作業は、その頃の自分やそれ以前の子ども時代にアクセスしているところがあるので、くるみざわさんに執筆の相談をすることが、半分カウンセリングのようになっていて(笑)。そういう事例をご存知だからこそ、今回、是非一緒に作業したいと思いました。
岩崎:山口茜さんが向き合おうとする題材に対して、ドクターの立場から、現実的にはこうであるというサジェスチョンをされているということですか?
山口:いえ、作家としてのご意見が大きいです。
岩崎:相談役という意味合いが強い?
山口:かなり(笑)
岩崎:それはすばらしいことですね。
■iaku 『walk in closet』 11月13日(金)~16日(月)
 岩崎:iakuは横山さんの個人ユニットで、今回は多彩な顔ぶれの俳優さんたちと新作を上演されます。
岩崎:iakuは横山さんの個人ユニットで、今回は多彩な顔ぶれの俳優さんたちと新作を上演されます。
横山:iakuとしては5本目の長編です。今回の作品は、セクシャル・マイノリティの問題を扱います。以前からこの題材に取り組みたいと思っていて、それをどうアウトプットできるのかを考えていました。それで、親の視点ならば、例えば、もし一人息子がゲイだったら…という視点でならいけるのではないかと気づき、あくまで家族の物語として描きます。今回は、本番2か月前に初稿を書き上げました。できるだけ戯曲にたくさんの人の眼をいれたいので、稽古が始まる前に、多くの人に読んでもらう環境をつくります。
岩崎:そういうブラッシュアップしていく仕掛けも、上演に向かう作業の中にあるわけですね。
横山:大阪と東京で、僕自身が初稿を朗読するイベントをやって、お客さんとゲスト演劇人から意見をもらったり、「クオークの会」(注)に提出して、信頼している劇作家に読んでいただき、意見をもらおうと思っています。
岩崎:「作者本読み」は、新劇の人たちはやっていたそうです。戯曲が文学である時代は作者が読んで俳優たちが聞いてという作業をされていたのですが、小劇場運動が始まって以降、それをやっている劇作家を私はほとんど知らないです。有名なのは唐十郎さんぐらいかな。故・中島陸郎さんの作者本読みを聞いたことがありますが、一人芝居の台本やったんですよ。横山さんの場合は、役名抜きで読むんですか?
横山:お客さんには、プロジェクターで投影して文字を追えるようにします。さすがに聞いているだけだと理解しづらいし、いちいち役名を読むとリズムが崩れるので、そういう仕掛けにします。
注)クオークの会/伊丹想流私塾出身者を中心に、戯曲のさらなる研鑽を目的として、定期的に集まり、互いの戯曲の講評しあうほか、年に一回、戯曲同人誌『海風』を出版している。
■アイホールでの初めての公演に向けて
岩崎:アイホールの空間性について、それぞれ何かアプローチをお考えですか?
はしぐち:僕は高さを意識します。客席をL字型に組んで、最前列を2尺(約60㎝)ほどあげて、舞台を少しだけ俯瞰して見下ろすかたちにする予定です。今までもこういう客席をアイホールで何度もみていますが、今回、ビルの谷間の公園が舞台なので、お客さんにビルの窓から公園の様子を覗き見している感覚になってもらえたらと思っています。そもそも、飛び降り自殺の死体が3か月間も見つからずに放置されていたという30年ぐらい前の新聞記事から着想を得たので、こういう舞台にしました。チラシの写真はその現場なんです、実は。
岩崎:落ちたのはビルの隙間でなく?
はしぐち:公園のど真ん中にある植え込みらしく、上半身は土の中で、下半身だけ少し出ていた状態だったようです。植え込みにずぼっと入っちゃったもんだから、誰にも気づかれず、3か月後に白骨化された状態で見つかった。そこは植え込みに対して背を向けるベンチしかなくて、サラリーマンやOLが普通にお昼ごはんを食べたりもしていたそうです。だから、今回は、お客さんが三方のベンチ全部が見える視点をつくりたいと思っているんです。
岩崎:都市の死角のような場所ですね。山口さんはどうですか。
山口:私は、まだ台本のことで頭がいっぱいで、演出のところまで考えがたどり着いてないです。
横山:僕は演出ではないので、空間のことを気にせずに書いています。今回はリビングが舞台なので本当はもう少し狭い空間でもいいのですが、iakuは今まで、カフェやプロセニアムの劇場でしか関西公演をしていないので、今回初めて、いわゆる小劇場空間の劇場でやってみようと。気合いを入れて、いろいろ無理を強いてやろうと思っています。
■作品の題材について
岩崎:この3作品は、都市の死角、実際の犯罪、ジェンダー問題と、現在進行形の社会的問題を扱っていらっしゃいます。もっとプライベートな、自分探しのようなことがキーワードになる可能性もあるかと思うのですが、それを選ばずに、こういった社会的な問題に目が向いているのはなぜなのか。作品を書くに至った出発点みたいなことをお伺いしたいのですが。
はしぐち:横山くんの戯曲には会話劇や物語というイメージがあるけど、コンブリ団にはそれがなかった。僕は今、敢えてそっちにシフトチェンジしようと思っています。ポストドラマが出てきた頃はすごく面白くて、言葉なんかどうでもいい、会話でやらなくても成り立つと思いました。今もその方法はもちろん有りだと思っていますが、最近は観客として観たとき、物語が欲しい、作品の根底に流れているドラマが欲しいと思うようになってきました。僕は自分の趣味趣向が常にうろうろ動いていますから、今の僕が観て面白いと感じるものがそれであるならば、自分が創るものもそれに従ったほうがいいと思い、今回は物語性のあるものを書こうと思いました。
岩崎:山口さんは、観客からわけが判らないと言われてきたのに、この作品を機に受け入れてもらえるようになったとおっしゃっていましたが、自分のなかで、作品に対するスタンスが変遷してきたのか、今回だけが特別なのか、どちらなんでしょう。
 山口:本質は20代から何も変わっていません。ただ、これでは人に伝わらないということが、なんとなく判ってきたというだけです。私、吉本新喜劇を観て育ってきているし、昔から普通にテレビドラマが好きでしたから、難しいことをしたいなんて一度も思ってないんです。
山口:本質は20代から何も変わっていません。ただ、これでは人に伝わらないということが、なんとなく判ってきたというだけです。私、吉本新喜劇を観て育ってきているし、昔から普通にテレビドラマが好きでしたから、難しいことをしたいなんて一度も思ってないんです。
岩崎:じゃあ、これからは判りやすいものを創っていきそう? それとも揺り戻しで判りにくいものになりそう?
山口:あっ、違うんです。常に自分では判りやすいものを創っていると思っていたのに、観た人には判りにくかったということで…。自分では論理的だと思っていても、そうじゃないということなんです。だから、私、論理的なことを書ける人とか、一幕物を書ける人、尊敬します。
岩崎:横山さんは、基本、一幕物ですよね。
 横山:そうですね(笑)。今回も時間や場所は動かさないです。時間や空間をとばせるのが演劇の強みですが、iakuの作品はほとんどが舞台上でリアルタイムに進みますし、それを自分に課しているところがあります。あと、あらすじに要約できないものを書きたいと思っています。人間を描いて、その関係性をつくって、そこに乗っかれば、ストーリーはいらないと思っていますし、そのことに挑戦したい。今回はジェンダーの問題を取り扱いますが、それが社会的だからというより、僕にとって頭で理解しているのに身体がついていけない問題だと感じるからです。東北の震災のとき、自分のなかでかなりの衝撃があって、何かをしなくちゃと頭で判っているのに何もしなかった。阪神大震災を思い返しても同じだった。出来事と自分との距離感がぼやけてしまって、そういう頭と身体が乖離することがどんどん起きている気がして、そのことをすべての作品で一貫して扱いたいと思っています。
横山:そうですね(笑)。今回も時間や場所は動かさないです。時間や空間をとばせるのが演劇の強みですが、iakuの作品はほとんどが舞台上でリアルタイムに進みますし、それを自分に課しているところがあります。あと、あらすじに要約できないものを書きたいと思っています。人間を描いて、その関係性をつくって、そこに乗っかれば、ストーリーはいらないと思っていますし、そのことに挑戦したい。今回はジェンダーの問題を取り扱いますが、それが社会的だからというより、僕にとって頭で理解しているのに身体がついていけない問題だと感じるからです。東北の震災のとき、自分のなかでかなりの衝撃があって、何かをしなくちゃと頭で判っているのに何もしなかった。阪神大震災を思い返しても同じだった。出来事と自分との距離感がぼやけてしまって、そういう頭と身体が乖離することがどんどん起きている気がして、そのことをすべての作品で一貫して扱いたいと思っています。
岩崎:「売込隊ビーム」の劇団時代と比べると、台詞のタッチは変わらないのに、作品内容というか見せ方はずいぶん変わりましたよね。
横山:あの頃は、ストーリーやギミックを考えたり、劇団員や観客の顔色を伺いながら創っていたような気がします。今は、自分が面白いかどうかを、判断材料にして、そこだけを頼りに創るようになりました。
後編では、それぞれの戯曲創作の方法について、話が広がりました。後編へ