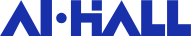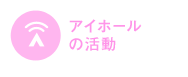アイホール・アーカイブス
刈馬カオス(刈馬演劇設計社) インタビュー
名古屋を拠点に活動する「刈馬演劇設計社」が、第19回劇作家協会新人戯曲賞を受賞した代表作『クラッシュ・ワルツ』で関西に初登場します。11月21日・22日のアイホールでの公演に先駆け、劇作家・演出家の刈馬カオスさんに当館ディレクターの岩崎正裕がお話を伺いました。
■『クラッシュ・ワルツ』について
岩崎:刈馬演劇設計社は、名古屋では中堅劇団として認知されていますが、関西ではまだまだ馴染みのない方も多いかと思います。まずは劇団のことや、この作品を書いた経緯などをお話しいただけますか。
刈馬:僕自身は、近畿大学で演劇を学んだあと、東京の劇団「青年団」に一年間俳優として在籍し、名古屋の七ツ寺共同スタジオ30周年記念事業の作・演出を担当したのを機に名古屋に戻り、演劇活動を続けてきました。「刈馬演劇設計社」は、名古屋で活動してきた劇団を解散して、2012年に僕一人で立ち上げたユニットです。以前は、派手な要素やお客さんを楽しませる要素を意識的にいれた作品を発表していましたが、『クラッシュ・ワルツ』では、今までのなかでいちばん地味な作品にしよう、とにかく会話を丁寧にして、登場人物がシンプルに対話する物語にしようと決めて書いた作品です。
岩崎:それまではどんな傾向の作品だったんですか。
 刈馬:社会派要素が強いものでした。例えば、カッターナイフで同級生を殺害した佐世保小6女児同級生殺害事件や酒鬼薔薇聖斗の神戸連続児童殺傷事件といった実際の事件を題材にしたものや、身体障がい者専用風俗をモチーフにした物語などです。ただ、事件や社会問題を扱いながらも、人間関係や個人のドラマを書くようにしていましたし、話が暗かったり難しかったりするのではなく、派手なエンターテインメントにすることを心掛けていました。『クラッシュ・ワルツ』は、そういったセンセーショナルな事件を取り上げるのではなく、どこにでもあるような交差点の交通事故を題材にしたことが、自分のなかでは地味だと感じています。初演(2013年)のとき、お客さんの評判が良くなくてもいいやと思っていたのですが、結局、この作品がいちばんお客さんにヒットし、わずか半年後に再演しました。
刈馬:社会派要素が強いものでした。例えば、カッターナイフで同級生を殺害した佐世保小6女児同級生殺害事件や酒鬼薔薇聖斗の神戸連続児童殺傷事件といった実際の事件を題材にしたものや、身体障がい者専用風俗をモチーフにした物語などです。ただ、事件や社会問題を扱いながらも、人間関係や個人のドラマを書くようにしていましたし、話が暗かったり難しかったりするのではなく、派手なエンターテインメントにすることを心掛けていました。『クラッシュ・ワルツ』は、そういったセンセーショナルな事件を取り上げるのではなく、どこにでもあるような交差点の交通事故を題材にしたことが、自分のなかでは地味だと感じています。初演(2013年)のとき、お客さんの評判が良くなくてもいいやと思っていたのですが、結局、この作品がいちばんお客さんにヒットし、わずか半年後に再演しました。
岩崎:そして今回が3回目の上演となるわけですね。どういった作品かお聞かせください。
刈馬:舞台は、どこにでもある交差点の、角に立っている家の和室になります。ワンシチュエーションなので、最初から最後までその和室で物語は進んでいきます。その交差点では3年前、男の子が亡くなる交通事故が起きていて、それ以来ずっと花が供えられています。実は加害者の女性が花を供えていたのですが、ある日、角に建っている家主の男がこの女性に、「この家を取り壊してマンションを建てたいのに、交差点に花があると販売価格に影響するから、やめてほしい」と頼みます。子供が通るのに危ない道だと思われるのも、人が亡くなった場所は気持ちが悪いと思われるのも困ると。そこに被害者の両親も加わって、花を供えることを「続ける」のか「やめる」のかを、それぞれの立場から、大人の事情をぶつけ合います。本当に、ギスギスというかゴリゴリというか、かなり緊迫感と緊張感のある対話が繰り広げられるので、僕は、「ノンストップ・トラフィック・サスペンス」と呼んでいます。
岩崎:平田オリザさんが提唱している「現代口語演劇」でいうと、〝最初に本題から入ってはいけない″という方法論があるんですけど、この作品は、物語の冒頭10分以内で今お話しされた内容が展開しますよね。すごく早いという印象を持ちました。
 刈馬:物語における最大の問題は何なのかを、できるだけ早いタイミングで観客に見せたいと僕は思っています。これは何の話なのかを冒頭で明確に提示したうえで、登場人物たちの水面下の会話や、もっとむき出しの対話に結び付けていきたい。だから、「会話」は「たわいもなく話すこと」、「対話」は「何かの目的に対して話すこと」と、区別して書いています。
刈馬:物語における最大の問題は何なのかを、できるだけ早いタイミングで観客に見せたいと僕は思っています。これは何の話なのかを冒頭で明確に提示したうえで、登場人物たちの水面下の会話や、もっとむき出しの対話に結び付けていきたい。だから、「会話」は「たわいもなく話すこと」、「対話」は「何かの目的に対して話すこと」と、区別して書いています。
岩崎:確かに、観る側にとって非常に明確な作品です。登場人物は5人のみですか。
刈馬:角の家の夫妻、被害者の両親と加害者の女性の5人です。
岩崎:ワンシチュエーションとして、徹底した定点で描かれているのも特徴ですし、ひとつひとつのピースが短い印象もあります。
刈馬:この作品は、必要最低限のセリフで、どんどん次に展開していくよう意図的に書きました。以前はそうではなく、無駄なセリフも書いていたのですが、どうもそういうセリフが苦手だと気づきまして。どうしても間延びしたり、「この時間は何だ?」という感じになってしまったんです。劇作家協会新人戯曲賞の選考会で、選考委員の佃典彦さんが、「ワンシチュエーションで、カメラの長廻しをしているような芝居は、映画でもできると思われがちだけど、それこそが演劇なんだよ」とおっしゃられて、そういう考え方もあるんだと嬉しかった覚えがあります。
■セリフの冗長性を意識する
岩崎:登場人物など、戯曲はとてもチェーホフ的だと思いましたが、演劇や戯曲の方法論を選択するにあたって、誰に影響を受けたのか興味が湧きました。例えば、創作に苦しくなったとき、ここに戻ってしまうみたいな原点のようなものはありますか。
刈馬:別役実さんの戯曲は、苦しくなったときに読むと「なるほど」と思うことが多いです。あと、無駄な会話がすごくうまくて勉強になるのはケラリーノ・サンドロヴィッチさんです。
岩崎:別役さんは不条理ですよね。
刈馬:僕の作風とは全然違うんですけど(笑)。
岩崎:台本をパッと見たときの、余白の面積が別役さん的だと思いました。一人が喋る分量は少ないのに、喋り出したら怒濤のごとく喋るというのも、別役戯曲の作法というか。会話の応酬のリズムが感覚として体に入っている気がします。
 刈馬:平田オリザさんにも影響を受けました。ただ、オリザさんのセリフは冗長率が高くて、本題を話し始めるときに、「えっと」とか「あー」が必ずといっていいほどついてくるんですよね。僕は、この戯曲の初演のときは、「えっと」をできるだけ排除して、相槌としての「あー」はあっても、「あーそれで」のセリフは「それで」から始めるよう、できるだけ細かく無駄を省くようにしました。ただ今回はその部分を書き直して、もう少し会話的にといいますか、最短距離を通らないようにしました。これまでの上演では、作品がアクセルをべた踏みするか急ブレーキをかけるかみたいな極端なことになっていて。迫力はあったんですけど、もう少し緩急のバリエーションをつけたら、もっとこの物語が豊かになるのではないかと思ったんです。結果、15分ぐらい上演時間が延びて80分程度になりました。
刈馬:平田オリザさんにも影響を受けました。ただ、オリザさんのセリフは冗長率が高くて、本題を話し始めるときに、「えっと」とか「あー」が必ずといっていいほどついてくるんですよね。僕は、この戯曲の初演のときは、「えっと」をできるだけ排除して、相槌としての「あー」はあっても、「あーそれで」のセリフは「それで」から始めるよう、できるだけ細かく無駄を省くようにしました。ただ今回はその部分を書き直して、もう少し会話的にといいますか、最短距離を通らないようにしました。これまでの上演では、作品がアクセルをべた踏みするか急ブレーキをかけるかみたいな極端なことになっていて。迫力はあったんですけど、もう少し緩急のバリエーションをつけたら、もっとこの物語が豊かになるのではないかと思ったんです。結果、15分ぐらい上演時間が延びて80分程度になりました。
岩崎:俳優との作業はどういう感じで展開されているのですか?
刈馬:「とにかく“目的”で喋ってくれ。感情よりも“目的”だ」と伝えています。感情が優先されて目的を後に回すと、そのシーンがつまらなくなるんです。だから、このセリフで相手にどういう影響を与えたいのかを忘れないで欲しいと言っています。
岩崎:まさにそのためのテキストだよね。冗長率が低いということは、目的で対話ができるように書かれている。
刈馬:はい。会話よりも「対話」です。
岩崎:初演で作品を立ち上げるとき、俳優は窮屈がったりしませんでしたか?
刈馬:リアクションをどこに挟んだらいいか、わからなかったようです。だから、セリフのあたまにつける呼吸の変化を、今までは「えっと」とか「あっ」とか発語することで行っていたのを、発語せずに呼吸だけで変化してほしい、今まで無意識に行っていた呼吸の変化を意識的にすることで処理してほしいと伝えました。
岩崎:おもしろいね。刈馬さんはこの作品で舞台美術も担当されていますが、アイホールという劇場空間はいかがですか。
刈馬:この作品は、ちょっと広めの空間にポツンとある感じのほうが合っている気がします。僕自身が、そもそもタッパ(高さ)の高い劇場がすごく好きなので、ツアーに向けて舞台美術も少し変えました。コンセプトの部分、特に装飾を変えて、タッパの高い空間を意識してデザインしましたので、アイホールは特に合うんじゃないかなと思っています。
岩崎:劇場の広さは変わっても、俳優の演じるエリアは変わらないから、広めの空間の中にポツンと浮島のように劇世界がある感じですね。
刈馬:そうですね。
■これからのこと
岩崎:『クラッシュ・ワルツ』以降、刈馬さんの戯曲創作は、対話劇になっていったんですか。
 刈馬:はい。以降の2作品は意識的にそうしました。上演時間もかなり短めに、無駄を省く感じで。とにかく、この作品でつかんだ何かを手放したくない、もっと深めたい、進化させたいと思って書きました。今は「対話」よりも、そこにどう「会話」を混ぜていくかに興味があります。その成果を今回の改訂版でも活かしています。
刈馬:はい。以降の2作品は意識的にそうしました。上演時間もかなり短めに、無駄を省く感じで。とにかく、この作品でつかんだ何かを手放したくない、もっと深めたい、進化させたいと思って書きました。今は「対話」よりも、そこにどう「会話」を混ぜていくかに興味があります。その成果を今回の改訂版でも活かしています。
岩崎:この作品って30代半ばで書かれたんですよね。これは僕の個人的な見解だけど、その時期につかんだ文体は一生モノだと思っています。僕が『ここからは遠い国』(1996年初演。第4回OMS戯曲賞受賞)を書いたのも同じ年齢のころで、この文体でこの方法論で進めようと意識するきっかけでした。今日お話を聞いて、ご自身の方法論について、随分、明確になっていらっしゃると感じましたので、やっぱり作家って30代半ばが勝負どころなんだと改めて思いました。
刈馬:確かに“つかんだ”という感覚があります。実はこの作品を書くまで、4年間ぐらいスランプの時期があったんです。どんなに書いても自分でも面白くないとわかりましたし、周りからの評判も悪い。20代後半は名古屋の注目株として、もてはやされたりした時期もあったんですが、スランプのころは「あいつはもう終わったな」と揶揄されたり動員も減ってしまったり。でもそのときも、技術的には昔よりも高くなっているはずだと思って書き続けました。『クラッシュ・ワルツ』を書いて、そこまでの4年間で模索していたことが、ガーッと自分の中でハマっていった感覚があって、これ以降、書くのがすごく楽になりました。
岩崎:多くの劇作家が体験してきたであろう道をすべて歩んだっていうかんじですね。なんだか、自分の話を聞いているみたい(笑)。それで、この作品で第19回劇作家協会新人戯曲賞を受賞された。人に評価されると、まだやっていていいんだという自己肯定観も芽生えるでしょ。
刈馬:はい。実は劇作家協会新人戯曲賞の選考会では、票が割れたんです。そのとき鴻上尚史さんが、「感性で評価したら、みんな感性が違うんだから話はまとまらない。劇作家が揃って話をしているんだから技術の話をしよう、技術で評価しよう」とおっしゃったんです。そうしたら僕の作品を推していなかった選考委員も「技術ならそりゃ『クラッシュ・ワルツ』だよ」と言ってくださって。それがものすごく嬉しかった。感性を褒められるよりも、技術を褒められたほうが僕は本当に嬉しくて、「やった!」と思いました。
岩崎:作家って、才能や感性を評価されたい反面、やっぱり技術を評価されたいよね。職人になりたい部分があると思うんだ。
刈馬:ありますね。誰も気づかないだろうけど、この台詞のこの組み立て方がめちゃくちゃ上手くいっているとか。
岩崎:このシーンでここまでしか語らないことが、実はここの伏線になっているんだよ、とかね。自分だけの密かな歓びを積み上げていくのが対話劇の醍醐味だったりする。
刈馬:ほんと、そうですよね。
岩崎:今はそれを積み重ねている最中だと思うんですが、ご自分で集団を持とうとは思わない?
刈馬:集団を持つと俳優の人数に縛られて書くことになるという思いもあって、もう少し、一人ユニットとして活動したいと思っています。とはいえ、今もある程度、声をかける俳優は決まりつつあるのですが(笑)。僕自身、集団を持ったときに、自分のわがままより集団が優先されるべきと思っていたのも理由のひとつです。決定権はあっても、作家や演出家はあくまで芝居をつくるためのひとつのパーツでしかないと思うので。でも、ユニットであれば、僕のわがままや思いつきを優先して進めることができる。だから、自分のわがままにあと数年取り組むことができたら、そのあと集団についてやっと考えられるような気がしています。
■関西公演にむけて
 岩崎:僕は最近、名古屋の演劇状況に触れる機会が多いのですが、名古屋には、北村想さんをはじめ、佃典彦(劇団B級遊撃隊)さんや平塚直隆(オイスターズ)さん、そして天野天街(少年王者舘)さんのように、独特の世界観でやっていらっしゃる方が多い印象を持っています。この作品のような、冗長率の低いギュッと絞られたような対話劇というのは珍しいんじゃないですか。
岩崎:僕は最近、名古屋の演劇状況に触れる機会が多いのですが、名古屋には、北村想さんをはじめ、佃典彦(劇団B級遊撃隊)さんや平塚直隆(オイスターズ)さん、そして天野天街(少年王者舘)さんのように、独特の世界観でやっていらっしゃる方が多い印象を持っています。この作品のような、冗長率の低いギュッと絞られたような対話劇というのは珍しいんじゃないですか。
刈馬:確かに名古屋は、不条理といいますか、少し脱力した感じのところがあって、ちょっとはぐらかすような風潮があります。対話を意識したり、取り入れたりした作品は、最近は若手からも出てきていますが、ここまで緊迫したぶつかり合いをする対話劇は、僕がいちばん極端な例だと思っています。
岩崎:関西も独自の進化系を辿っていると思いますが、こちらでは会話・対話劇派も多いんです。だから、関西でこの作品を上演すると、この緊張感でこの対話劇、なるほどこれは成立する、と見てくれる観客が多い気もしています。
刈馬:大学4年間を関西で過ごしたので、いつかこちらでの公演を実現したいと願っていました。関西の演劇事情に詳しいわけではないですが、エンターテインメントのお芝居もあれば、会話や対話で進めていくスタイルもあり、名古屋に比べて色分けがはっきりしている印象を持っています。僕は、映画のホラーやサスペンスと同じく、演劇の対話劇やサスペンスもエンターテインメント性が高いものだと思いますし、派手ではないですが、それを意識して書いています。きっと関西の観客のみなさんも、面白がってくれるのではないかと期待しています。
(2015年10月 大阪市内にて)