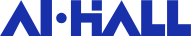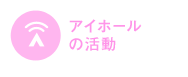アイホール・アーカイブス
平成28年度 次世代応援企画break a leg 参加劇団インタビュー

AI・HALL共催事業として、今年度も「次世代応援企画break a leg」を開催いたします。
参加する2劇団よりそれぞれ代表のみなさんと、アイホールディレクター岩崎正裕より、本企画および各公演についてお話いただきました。
◇アイホールディレクターより企画趣旨について
岩 崎:「次世代応援企画break a leg」は、2012年度から開催しております。
昨今の関西では、若手の新しい劇団が出てきても、経済的になかなか厳しい状況にあります。カフェ公演や、100人以下のキャパシティの劇場…いわゆる小劇場で上演をしてみよう、というところから、野心を持って中劇場、大劇場へ打って出よう、といった集団が、なかなか生まれにくいというような環境にあります。そのなかでアイホールは、中劇場の拵えも出来るホールですから、若手に挑戦してもらう機会を出来るだけ設けないと、登場するのが中堅以上のカンパニーばかりになってしまうような現状です。ですので、質の高い作品をつくっている若い表現者に門戸を開くために、この「break a leg」という企画は立ち上がりました。そこから平成27年度までにたくさんの集団に登場していただきました。昨今では、例えばオイスターズ(2013年度参加)にしても、FUKAIPRODUCE羽衣(2014年度参加)にしても、アイホールをツアーに組み込んでくださるようになってきており、どんどん定着してきているという感があります。最近は、東京、中部、九州などからの応募も増えておりまして、逆に言うと、関西からの応募が若干少ないという…。また若手カンパニーの意欲を刺激するためにつくった企画であるにも関わらず、若手からの応募が少なくなってきているという現状もありますが、今回は9団体の応募がありました。中に強力な団体がふたつありまして、それが今回参加していただく「夕暮れ社 弱男ユニット」と「ミナモザ」です。
まず5月に登場していただきます、「夕暮れ社 弱男ユニット」の村上慎太郎さんから作品についてお話しいただきたいと思います。
■夕暮れ社 弱男ユニット『モノ』について

村 上:「夕暮れ社 弱男ユニット」は、2005年に京都造形芸術大学舞台芸術学科の学生でつくった劇団です。最近は、京都芸術センターや、元・立誠小学校などを中心に活動していますが、今年は三重県文化会館やこまばアゴラ劇場などでも公演して、幅を広げて勢い付けていきたいな、と思っています。
どういう作品をつくっているかといいますと、例えば『プール』(2014年)という作品では、土嚢袋を400袋くらい用意して、それを投げながら俳優が物語を演じることが出来るかということにチャレンジしました。ほかには、観客席のパイプ椅子を俳優が投げて、その負荷が身体にかかった状態で演じたり、80分間のお芝居中、俳優が転がり続けながら演じたり…、そのなかで、新しい物語の見せ方を追求するような作品をつくっています。そもそも、なぜそういう作風になったかというと、実は劇団発足当初から、海外で上演したいという野望がありまして、身体や物語の見せ方を何か新しい角度で出来ないかと、やり口ばかりを追求してきました。それで、「海外でやりたいんです」という話をしていたら、昨年、大阪ドイツ文化センターのリーディング企画をやる機会を得ました。僕と同世代でまだ日本に紹介されていない作家さんの戯曲を上演するという企画です。昨年の5月にアイホールのカルチャールームでリーディング上演をしたのですが、それがフィリップ・レーレさんの『モノ』という作品でした。
この台本を選ぶにあたって、いろんなドイツ戯曲を読みました。僕が今、興味があるのが「喜劇」で、「喜劇を書かれている作家さんの作品を紹介してほしい」とお願いしたところ、この『モノ』という戯曲をご紹介いただきました。リーディング公演のときに作者のフィリップ・レーレさんが来日されたんですけど、「子どもに見せられるような、でも子どもだましではない児童劇として書きました」と仰っていて、それがすごく印象的でした。非常にわかりやすく、見やすく書かれていて、ドイツの同世代の作家はこういうことを考えているんだと取っつきやすい作品でして、今回の上演がすごく楽しみです。
 最初はアフリカの綿花畑から物語は始まります。畑で栽培された“綿”が引き伸ばされたり繋げられたりして、中国で大量生産のTシャツになります。そのあとドイツに渡って、販売されて、ドイツ人が着ます。でも穴が開いてしまう。ドイツではTシャツに穴が開くと、専用のポストに入れるというシステムがあるらしいんですけど、その穴開きTシャツが結局アフリカに渡っている、と。モノは生まれた場所にまた戻ってくるのかもしれない、またそこから旅が始まるのかもしれない…。そんな物語を通じて、アフリカでは農薬をまいて大規模に農業をしないと食べていけない状況であったり、ヨーロッパがアフリカに武器を売って、国連がそれを折り曲げて使えないようにしている現状だったり、そういう大きな貧困問題から紛争の問題までが描かれます。それと同時に、この作品の面白いところは、男女の痴情のもつれや、商売のやり方―スピーディにやるのがいいのか、ゆっくりがいいのか―といった、小さなもめごとも描いているところです。小さな問題から大きな問題まで取り扱いながら、世界を旅する作品になっています。アメリカ人、ドイツ人、中国人などたくさんの人種が出てくるのですが、稽古していると、「日本というのはやっぱり島国だなあ」と漠然と感じていて、なぜそう感じるのかを上演を通して見つけたいと思います。日本人が国を越えるときの距離感と、ドイツ人が国を越える距離感はやっぱり違うなあとか、そういう、世界に対して自分たちがどう立っているか、という“立ち位置”がわかるような作品だと感じていて、日本の作家には書けないような感覚があるような気がします。今、世界で、ドイツで考えられていることを、ぜひ劇場へ観に来てほしいです。
最初はアフリカの綿花畑から物語は始まります。畑で栽培された“綿”が引き伸ばされたり繋げられたりして、中国で大量生産のTシャツになります。そのあとドイツに渡って、販売されて、ドイツ人が着ます。でも穴が開いてしまう。ドイツではTシャツに穴が開くと、専用のポストに入れるというシステムがあるらしいんですけど、その穴開きTシャツが結局アフリカに渡っている、と。モノは生まれた場所にまた戻ってくるのかもしれない、またそこから旅が始まるのかもしれない…。そんな物語を通じて、アフリカでは農薬をまいて大規模に農業をしないと食べていけない状況であったり、ヨーロッパがアフリカに武器を売って、国連がそれを折り曲げて使えないようにしている現状だったり、そういう大きな貧困問題から紛争の問題までが描かれます。それと同時に、この作品の面白いところは、男女の痴情のもつれや、商売のやり方―スピーディにやるのがいいのか、ゆっくりがいいのか―といった、小さなもめごとも描いているところです。小さな問題から大きな問題まで取り扱いながら、世界を旅する作品になっています。アメリカ人、ドイツ人、中国人などたくさんの人種が出てくるのですが、稽古していると、「日本というのはやっぱり島国だなあ」と漠然と感じていて、なぜそう感じるのかを上演を通して見つけたいと思います。日本人が国を越えるときの距離感と、ドイツ人が国を越える距離感はやっぱり違うなあとか、そういう、世界に対して自分たちがどう立っているか、という“立ち位置”がわかるような作品だと感じていて、日本の作家には書けないような感覚があるような気がします。今、世界で、ドイツで考えられていることを、ぜひ劇場へ観に来てほしいです。
岩 崎:日本では翻訳劇って、それこそ明治・大正を通じていろいろあるわけですけど、翻訳劇の新しいあり方を模索されるという演劇的野心に期待を持って、今回、「夕暮れ社 弱男ユニット」を推薦させていただきました。上演が楽しみです。
■ミナモザ『彼らの敵』について

瀬戸山:「ミナモザ」というのは、わたしが主宰で2001年に旗揚げをしました。今も基本的にはひとりです。ただ、継続的に一緒につくるメンバーというのがいて、ほかの劇団に所属している人もいるんですが、座組のうち半分くらいは毎回出ていただいている人です。特徴として、集団創作にとても重きを置いていて、演出の最終決定はわたしがするんですが、とにかく稽古場で試行錯誤をして、ああでもないこうでもないとみんなで言いながらたどりつく…みたいな形で作品をつくっています。
今回の『彼らの敵』という作品は、実際の事件をもとにしています。
ミナモザの舞台写真をずっと撮ってくださっている、服部貴康さんという写真家がいらっしゃいます。彼がかつてとある週刊誌の専属カメラマンだったということは知っていたのですが、それ以外のことはよく知りませんでした。10年くらいの付き合いののち、たまたま「人生のターニングポイントは何か」という話をしていたら、服部さんが「誘拐かな」と突然仰ったんです。「実は大学生の頃に、パキスタンで強盗団に誘拐されたことがあるんだ」と仰って…。「どうして今までその話をしなかったんですか」と聞くと、「タイミングが合ったら話すけど、基本的にはまだ整理がついてないからあまり話さない」と仰っていて、ただ、「何かしらの方法で、自分の体験したことをいずれ世に出したい。何だったら、瀬戸山がノンフィクションとして書いてよ」みたいなことを言われたので、「本にはできないかもしれないですけど、演劇にはしたいです」と言いました。そこから2年間ぐらいかけて、服部さんの話を伺いました。彼は、この事件のことを許せないと思っていました。でもそれは、誘拐されたこと自体ではなくて、帰国してからマスコミに追いかけられて日本中からバッシングされた、そのことをずっと許せないと思っている。話を伺った時点でもう20年以上経っていたんですけど、実際にその時に届いた手紙のコピーを服部さんは取っていて、その手紙というのが、この作品の本当の出発点になっています。ある60代の女性からのもので、「あなたたちがやったことは日本の恥だ」ということが、きれいな字で延々と書かれている。会ったこともない20代の若者に対して、こういう手紙を書くエネルギーはどこから湧いてくるんだろうと思って…。「この手紙を書いた人にわたしも怒りを感じるから、それを芝居にしたい」と思いました。バッシングの手紙が来るきっかけになったのは、元々週刊誌の記事が原因でした。普通の大学生を追い詰めるような記事です。最初はそれに対する怒りの気持ちからも戯曲を書いていました。…ですが、戯曲を書くうちに、ひとつ理解できないことが出てきました。服部さんが大学卒業後に選んだ職業が、まさにその「週刊誌カメラマン」であったということです。「そんなに嫌な目にあったのに、なぜ同じ仕事をしているんですか」と取材のたびに何度も伺ったんですが、そうすると服部さんは毎回「パパラッチに追われた経験のある人間しか撮れないものがある」と仰る。最初そういうものなのかもしれないと思ってたんですけれども、だんだん「なんか変じゃないかな」と思い始めました。
■“彼ら”とは? “敵”とは、誰?
 瀬戸山:『彼らの敵』というタイトルは初期から決めていました。服部さんから見て例えば手紙を送ってきた人々は“敵”、もしくはそういった人たちから見て自由に冒険旅行をして捕まった服部さんは“敵”、お互いがお互いを敵だと考えているということを描こうと思いました。でも結局本当の“敵”は彼自身の中にあることがわかってきました。だから「このお芝居は最終的にはあなたを救うものにしたいけれど、途中に少しつらい描写もあります」と服部さんにお話ししました。そして、もうひとつフィクションの存在としてわたしにとても近い「ライターの女」という役を出すことにしました。彼女は、倫理的にいいのかなと思いつつ、自分にすごく言い訳をしながら男性週刊誌で働いているという女性で、その彼女と服部さんを対峙させました。ふたりはすごく傷つけあうんですけれども、そこから「本当の問題って何だろう」ということが見えてくるような芝居にしました。
瀬戸山:『彼らの敵』というタイトルは初期から決めていました。服部さんから見て例えば手紙を送ってきた人々は“敵”、もしくはそういった人たちから見て自由に冒険旅行をして捕まった服部さんは“敵”、お互いがお互いを敵だと考えているということを描こうと思いました。でも結局本当の“敵”は彼自身の中にあることがわかってきました。だから「このお芝居は最終的にはあなたを救うものにしたいけれど、途中に少しつらい描写もあります」と服部さんにお話ししました。そして、もうひとつフィクションの存在としてわたしにとても近い「ライターの女」という役を出すことにしました。彼女は、倫理的にいいのかなと思いつつ、自分にすごく言い訳をしながら男性週刊誌で働いているという女性で、その彼女と服部さんを対峙させました。ふたりはすごく傷つけあうんですけれども、そこから「本当の問題って何だろう」ということが見えてくるような芝居にしました。
再演のときは、その前年にIS(イスラム国)に日本人ふたりが拉致されて殺されてしまう事件が起きて、そのときにやっぱり、「自己責任」という言葉が間違った意味でマスコミに出てきました。服部さんの時代はインターネットがなかったけれども、今はネットでそういうものがどんどん暴走してしまうというのを目の当たりにして、なぜ死んでしまった人や、その人を助けたかった人たちを傷つけなきゃいけないのかとすごく感じて、この作品はやり続けようと思いました。再演では、「パキスタン」という国について、もう少し掘り下げました。パキスタン人の通訳の方に入っていただいて、台本を書き直し、イスラム教や慣習について、改めて全体を監修してもらいました。今もやはり社会の状況はまったく変わっていないと思うので、この作品はとにかくやり続けようと決めています。
岩 崎:映像で見せていただいたのですが、最後、服部さん役の方と、ライターの女性の対話のリアリティがすごいなと思いました。あんなに手に汗握ったのは久しぶりというくらい、面白かったですね。いま瀬戸山さんが仰っていたようなことが舞台からありありと伝わってきました。やっぱり作者の生の言葉でこうやってお聞きすると、上演が本当に楽しみですね。
■リーディング劇『ファミリアー』について
 瀬戸山:あともうひとつ、今回は『ファミリアー』というリーディング作品を、6月26日11時に1回だけですが上演します。『彼らの敵』のモデルの服部貴康さんは、動物愛護センターや保健所にたどりついた犬たちの写真をずっと撮り続けていて、写真集を出しています。私は、東日本大震災が起きたときに、「生きていく人と死んでしまう人の違いは何なのだろう」と考えてわからなくなっていた時期があって、そのときにふとその写真集の存在を思い出して、あれをもとに台本を書かせてもらおうと思って書きました。三人の男性が、犬と、愛護センターで働く職員の人たちの両方を交互に演じるという40分間の作品です。初演以来、主に小中学校で上演を重ねていて、小学校高学年くらいから大人まで、観ていろいろ考えていただける作品です。この機会に関西の皆さんに知っていただけたらと思います。
瀬戸山:あともうひとつ、今回は『ファミリアー』というリーディング作品を、6月26日11時に1回だけですが上演します。『彼らの敵』のモデルの服部貴康さんは、動物愛護センターや保健所にたどりついた犬たちの写真をずっと撮り続けていて、写真集を出しています。私は、東日本大震災が起きたときに、「生きていく人と死んでしまう人の違いは何なのだろう」と考えてわからなくなっていた時期があって、そのときにふとその写真集の存在を思い出して、あれをもとに台本を書かせてもらおうと思って書きました。三人の男性が、犬と、愛護センターで働く職員の人たちの両方を交互に演じるという40分間の作品です。初演以来、主に小中学校で上演を重ねていて、小学校高学年くらいから大人まで、観ていろいろ考えていただける作品です。この機会に関西の皆さんに知っていただけたらと思います。
Q.アイホールのような大きい空間で上演するのは初めてですか? また、どういうふうに空間を使う予定でしょうか。
瀬戸山:ミナモザは、別の作品では東京のシアタートラムと座・高円寺でやらせていただいていて、アイホールサイズの空間でやったことがないわけではないのですが、この『彼らの敵』は6人しか出てこなくて、すごく小空間でつくっているので、その密度をどうやってアイホールでやろうかと考えています。ひとつの円を描いた舞台美術の中からほとんど主人公が出なくて、そこにたくさんの人が出たり入ったりする芝居なのですが、この中でずっとぐるぐる迷い続ける主人公をきちんと見せるようにやりたいです。これからやり続けるにあたって、アイホールのようなワンサイズ大きい劇場で改めてつくることで、今後もいろんなところで上演できる形をつくっていけたらと思っています。
 村 上:僕らは、アイホールのサイズは初めてです。まずアイホールの床全体に、ドイツを中心とした世界地図をドンと置きます。あとは今回、いろいろ吊ることが出来るので、吊りもので勝負しようかなと思っています。で、実はアイホールには、ホリゾントの前にスクリーンが隠れてて、自動で降りてきて自動で開くんです。夕暮れ社がアイホールでやるんだったら、そういう新しいギミックを使ってみたいなという野心があります。それから、小道具も全部吊っちゃおうかなと。椅子なんかも全部吊っちゃって、そのシーンが始まったら降りてくるとか、上の空間で見せたりとか、そういうようなことを考えています。
村 上:僕らは、アイホールのサイズは初めてです。まずアイホールの床全体に、ドイツを中心とした世界地図をドンと置きます。あとは今回、いろいろ吊ることが出来るので、吊りもので勝負しようかなと思っています。で、実はアイホールには、ホリゾントの前にスクリーンが隠れてて、自動で降りてきて自動で開くんです。夕暮れ社がアイホールでやるんだったら、そういう新しいギミックを使ってみたいなという野心があります。それから、小道具も全部吊っちゃおうかなと。椅子なんかも全部吊っちゃって、そのシーンが始まったら降りてくるとか、上の空間で見せたりとか、そういうようなことを考えています。
岩 崎:アイホールで立ち上げる作品は、アイホール専用に間口を広げたりすると大変面白いことが出来るし、逆に、再演で持ってくるときの成功の秘訣は“変えない”ことだと僕は思ってます(笑)。
瀬戸山:はい、わたしもそう思ってます(笑)。
岩 崎:客席の列の数はアゴラ劇場とそんなに変わらないので、俳優の演技なんかもあまり変えないで成立するのがアイホールの特徴だと思っていますので、ぜひそのままで(笑)。
Q.『彼らの敵』が書き上がったときの服部さんの感想は?
瀬戸山:服部さんにとって一番しんどいシーンというのがあって、稽古にいらっしゃって観たときは、「瀬戸山は意地悪だあ」と言われました。ただ、服部さん自身はこの作品があって、ちょっとひとつ荷が下ろせた感じもあるみたいで、彼はそのあとすごく人生が変わり始めたんです。一度迷いすぎて、家財道具を捨てて、家も捨てて、飼っていた猫をわたしに預けたりされてたんですけど、この数年のあいだに結婚されて、岐阜に引っ越して、落ち着いていらっしゃいます。服部さんとわたしにとって、そういうタイミングだったんだなって思います。
Q.ドイツの喜劇というのは、日本の喜劇とは違う感じですか? どういったところで笑いを取ってるんでしょうか。
村 上:日本でいう「笑いの構造」みたいなものはドイツにも確実にあって、ただ即物的な、いわゆる出オチとかそういった笑いよりは、人物の悲哀とか、人物の考えがずれていく面白さ、みたいなことを「喜劇」と呼んでいます。世界のいろんな人の考えがずれていくことで、それが「喜劇」に見えるという、日本とは少し違った感覚でありつつも、日本にもある笑いの構造が発掘できたりして、そういうのはすごく新鮮です。
Q.瀬戸山さんはいつも、今の社会や現実の中からテーマを抽出しようとされているんでしょうか。
瀬戸山:“今”のことをやりたい、というのはあります。今の空気だったり、同調圧力みたいなものだったり、そういうものを書きたいと思っています。「演劇でしか出来ないドキュメンタリーって何だろう」といつも考えていて…単純なドキュメンタリーだったら、映画や小説のほうがそのままを描けるけれども、でも演劇でしか出来ない、本質を描く方法があるんじゃないか、というのは考えながらやっています。
Q.「夕暮れ社 弱男ユニット」で、村上さんの書いた作品以外をするのは初めてですか? また既成の戯曲を演出する難しさはありますか?
村 上:劇団で、自分の書いた作品以外をやるのは、今回が初めてのチャレンジです。翻訳ものというのも実は初めてです。演出するときに、他人が書いた戯曲だと思って演出するよりも、自分が書いた戯曲だと思って演出したほうがやりやすくて、そのほうが作品に血が通うような気がしています。「自分とは違う考えだから面白い」というよりも、自分の考えにしていくというか…。もちろん、戯曲を書き換えたりという意味ではなくて、自分が書いたように演出すると、力の抜けたいつも通りの作品になるかな、と。翻訳の堅苦しさみたいなものもあるんですが、そこで柔らかくなっていって、「喜劇」になればいいなと思っています。
Q.「break a leg」に関西からの応募が減っているとのことですが、その背景は?
岩 崎:背景は読めているんです(笑)。最初はものすごく応募が多かったんですが、毎回選ぶでしょ? そうすると選出された2団体は喜ぶんですけど、あとの団体は傷つくわけなんですよね。そこで、「じゃあ、もう出さない」という気持ちが働くのは、人間として無理からぬことだと思うんですよね。
瀬戸山:もったいない!
岩 崎:そうなんですよ。だから、「次出してくれたら、もうちょっと観たいな」と思ってた団体が、今年は出してこなくて残念…というのがあります。夕暮れ社さんは、初めての応募じゃないですよね?
村 上:…ばれましたね(笑)。実は3回目です。
岩 崎:そうすると、着々と成果を上げられていて、「いま面白いところに来てるな」と時系列で見られるわけなんですね。それを「もういいや」と諦めて、応募が減ってしまっているというのを、アイホールとしては次、どうしていけばいいかと考えているところです。
村 上:でも確かに、落ちたら傷つきますよねえ。
岩 崎:そうでしょ? 僕もつくる人間なのでわかるんですけど、落ちたらやっぱり傷つくんだよね。でもそこは、夕暮れ社さんのように、しつこく2回でも3回でも応募してくれたら、こういうふうに道が開かれるんだ、というイメージを…どうしたら持ってもらえるんでしょうかね(笑)。
村 上:僕らが頑張るしかないです(笑)。
岩 崎:「3回目の応募でいけたー!」みたいなことを言ってもらえると、とてもうれしいです。