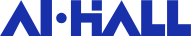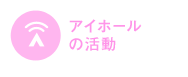アイホール・アーカイブス
劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』インタビュー
 9月21日・22日に提携公演として登場する劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』の上演に先駆け、劇作を担当した古川健さんと俳優の西尾友樹さんに作品についてお話しいただきました。
9月21日・22日に提携公演として登場する劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』の上演に先駆け、劇作を担当した古川健さんと俳優の西尾友樹さんに作品についてお話しいただきました。
■作品について

古川:『治天ノ君』は2013年に下北沢の駅前劇場で初演した作品で、大正天皇・嘉仁(よしひと)を主人公に、皇太子時代の青年期からその死までを描いた一代記です。物語は大きく分けて、嘉仁が青年期に明治天皇との軋轢や孤独を経て、天皇として即位し自我を確立するまでの前半と、病に倒れて皇太子(のちの昭和天皇)を摂政に立てるまでの後半から成っています。“治天の君”とは中世の日本史用語で、院政期に天皇家の実権を握った上皇や法皇の呼び名です。この話には、明治・大正・昭和と三人の天皇が登場するのですが、大正・昭和時代にも、明治天皇が呪縛のように大きな影響力を与えるので、このタイトルを付けました。でも、主人公は大正天皇です。松本紀保さん演じる大正天皇妃―貞明皇后節子(さだこ)がストーリーテラーとなり、昭和時代から明治・大正を振り返るといった構造で、回想として語られます。
なぜ大正天皇を題材にしたのかというと、近代天皇制以降、今上天皇で4人目ですが、そのなかでも今の我々にとっていちばん印象が薄い存在だと思うからです。僕自身、遠眼鏡事件(国会で勅書を丸め、遠眼鏡にして議員席を見渡したとされる事件)や、ちょっと頭が弱かったのではないかという俗説しか知りませんでした。ところが、政治学者の原武史さんが書かれた『大正天皇』(朝日新聞社刊)を読んで、実はそうではなかったと知り、一般的なイメージとは違う大正天皇を主軸にした物語を書いてみたいと思いました。調べていくと、明治天皇のように神秘性を持っていることを理想の天皇像としたときに、大正天皇はそこから外れるような人間性だったという記録が残っています。例えば、皇太子時代、巡啓として全国各地を旅したときに気軽に国民に話しかけてしまったり、昔の同級生の家を突然訪問したり…。そういうエピソードを拾っていくと、とても魅力的な人間味溢れる人だと感じましたし、そういうことが知られていないのはもったいないと思いました。僕は歴史的な事件や人物を題材に作品を書いていますが、決して史実を忠実に再現したいのではありません。生身の人間らしさがふっと浮かびあがってくるエピソードがあれば積極的に取り入れていますが、基本的には創作ですし、描きたいのは 、今の我々とは違う歴史状況のなかで、人間としてどう生きたか、どんな思いを持ち、どんな苦悩があったのかということです。「天皇」という存在は、戦後にこそ“象徴”となりましたが、戦前は“現人神(あらひとがみ)”だったわけです。そういう存在が、ひとりの人間として、立ったり座ったり、人と話をしたり、物事を感じて、悲しんだり喜んだりするさまを描き、それを演劇というナマの表現を使って、役者さんの肉体を通してお客様に届けたいと思っています。
、今の我々とは違う歴史状況のなかで、人間としてどう生きたか、どんな思いを持ち、どんな苦悩があったのかということです。「天皇」という存在は、戦後にこそ“象徴”となりましたが、戦前は“現人神(あらひとがみ)”だったわけです。そういう存在が、ひとりの人間として、立ったり座ったり、人と話をしたり、物事を感じて、悲しんだり喜んだりするさまを描き、それを演劇というナマの表現を使って、役者さんの肉体を通してお客様に届けたいと思っています。
もうひとつ、「戦前」という時代の流れを描きたいと思いました。我々は明治・大正・昭和前期を「戦前」と一括りでとらえてしまいがちですが、やっぱりそれぞれの時代の特徴があるわけです。明治天皇と昭和天皇に挟まれた大正天皇を取り上げることで、明治から大正、大正から昭和という時代の流れが描けるのではないかと考えました。また、原敬や大隈重信や牧野伸顕といった実在の政治家を登場させることで、各時代の天皇をとりまく政治家たちが、何を考え、どう時代を動かしていったのかを、わかりやすく板の上にのせたいとも思っています。
■「天皇」を演じる

西尾:大正天皇を演じるんだという気負いはありません。どちらかというと、泣いて、笑って、怒って、身体を悪くしても天皇という位にしがみつこうとする、ひとりの人間を舞台上に引きずり出すんだという思いのほうが強いです。それは明治天皇と昭和天皇を演じる二人も同じです。もともと僕たちの劇団は、イメージで役を演じないということをすごく大事にしていて、目の前にいる人間と会話をし、シーンを重ねて、事件を重ねて、それが歴史に繋がっていくという創り方をしています。だから、皇室の話をするぞとか、タブーに切り込むぞというのではなく、丁寧に丁寧に人間のドラマにしていきたいです。ただ、お辞儀の仕方や手の組み方などの所作にはこだわっています。初演のときに、演出助手が皇室の作法やロイヤルマナーの本を探してきてくれたのですが、それを参考に毎日繰り返し稽古をして、そして、その所作にどこまで気持ちを載せていくか、思いをどれだけ滲み出していくかにトライしています。ちなみにその本には、周りへの気配りを偏らせないよう、意識の飛ばし方は360度ムラなくというのもあるんですけど…、それはさすがに会得できなかったです(笑)。
先日、平成天皇の生前退位のニュースがありましたが、この物語でも天皇を「やめる」「やめない」「やめろ」「やめるな」みたいな話が繰り広げられています。天皇って、文化や平和の象徴であって、かつ国の威信の象徴でもありますよね。だから「やめます」といって簡単にやめられるものでもない。物語の後半、嘉仁が髄膜炎という重い病気を患い、肢体不自由になって言語も危うくなり、記憶も飛び飛びになっていきます。それでも天皇という位にこだわる姿を演じてみて、きっと苦しんでいらっしゃったのだろうなと思います。
古川:史実として、大正天皇は晩年、皇太子(のちの昭和天皇)を摂政に立て、実権をすべて譲って引退します。ただ、そこに大正天皇の意思は無かったのではないかという学説があり、今回はそれを参考にしました。そうした葛藤を描くことで、彼の「天皇」という存在に対する思いや、運命に対してどう生きたのかという生き様が浮かび上がってくるのではないかと思っています。
西尾:病気の症状が、大正天皇自身に実際どのように出たのかはわかりません。だから、病気のことを調べ、こういう症状が出たら身体の半分はこうなる、歩き方はこうなる、喋り方はこのぐらい不自由になるというのをなるべくリアルにやりました。カタチを細かく決めて、不自由になってもここまでは立っていられる、座っていられる、歌うことができるという状態を、今回も嘘つくことなくやりたいと思っています。
古川:僕は、西尾くんの俳優としていちばん好きなところは再現性とこだわりです。キャスティングは演出の日澤に一任しているのですが、書いているときから大正天皇は彼にやってもらいたいと思っていました。病んでからの身体的な表現も西尾くんならごまかすことなく真正面からやってくれるだろうと思いましたし、逆に、青年期の颯爽としたところとの演じ分けも、彼なら信頼して託せると思いました。
西尾:僕自身は芸の幅が広いわけではないので、素直に相手役とどう繋がっていくのかを考えています。正直、最初に台本を読んだとき、どういう物語なのか掴みあぐねました。皇室の話だから、事件も起きないし、犯人もいない。でも、稽古をしていくと、この人のことを慕っているからこういう会話をするんだとか、怒られているけどこれは愛なんだなとか、そういう関係性がみえてきました。ただ、役者が立ち上げないとみえてこない関係性もあって…、難しい本だと思います。例えば、登場する政治家は本音を言わないから、そういう人間が大正天皇の周りを固めると、本当に天皇のことを慕ってくれているのか疑念が湧くんです。そういうところは古川さんに、政治家も思惑があるから天皇の前でそう発言するんだと教えていただき、繋がるように細かいところは埋めていきました。
■再演にむけての見どころ
古川:再演にあたり、改稿しようと読み直したのですが、ここを変えるとあそこも変えなきゃいけないとなってしまって…、結局このバランスを保ったままのほうがいいと判断し、初演からほぼ手を加えずに、あとは演出に委ねています。僕はもともと、長く書いてしまうタイプでして、この作品の初稿もそのまま上演すると3時間半ぐらいあったんです。初演のときは、稽古場でそれを三分の一ほど切ってもらい、2時間ぐらいになりました。カットしたり残したりする作業は僕が作家としてやるよりも、演出家が現場をみながら塩梅をとったほうが絶対によくなるだろうと思い、日澤に任せました。だから上演されたものをみると、僕の作品ではあるんですが、稽古場で演出家と現場の作業を経ていますので、僕一人だけのものとは言い難くもあります(笑)。
西尾:日澤さんの演出は、台本を切ることは情報量を減らすことではない、切った部分は役者が表現してくれという考えなので、初演でもカットした部分は役作りに活かしました。今回も、演出は、古川さんが初演から変えないと言った時点で、それでいくというスタンスをとったので、大きな変更はないです。ただ、初演よりも人間関係の見つめ方をもっともっときつく、煮詰まった作品にしようとは言っています。
古川:大正天皇と皇后節子の夫婦愛もこの物語の柱の一つです。今回も皇后節子を松本紀保さんにお願いしたのですが、本当に、皇室の方にしかみえないような高貴さがあります。そこはぜひとも劇場でみていただきたいです。
西尾:貞明皇后節子について書かれた本に、大正天皇の記述があるんです。例えば結婚式のときのエピソードで、緊張している節子のところに嘉仁が現れて、「すごく退屈だね、これあと何日続くんだろう」と話しかけてきて、それで節子さんの気持ちがすごく楽になったとか。紀保さんと、「こういう関係性、面白いですね」という話をしました。身体の悪い天皇と寄り添っている妻というより、そういう小さなエピソードを拾って拾ってつなぎ合わせて膨らませて、皇族というのではなく、どこにでもいる夫婦の姿をつくれたらと思っています。
■劇団について
古川:劇団チョコレートケーキは、俳優の近藤芳正さんのユニット「バンダ・ラ・コンチャン」と合同公演を今年1月に富田林市のすばるホールで行ったのですが、劇団単独での関西公演は今回が初めてです。僕たちは駒澤大学の劇研仲間が母体となって2000年に旗揚げした劇団です。旗揚げ当初は僕も演出の日澤も役者をしていました。ところが座付きの作・演出家がやめてしまい、誰かが書かなくちゃいけない状況になり、仕方なく僕が書くことになりました。最初はオムニバスの現代口語劇や、宮沢賢治をモチーフにしたものを書いていたんですが、もともとそういう状況で書き始めたので、どちらかというと書くのは好きじゃない(笑)。それで、自分の好きな歴史を題材にしたら、この苦しい作業が少しは楽になるんじゃないだろうかと思い、浅間山荘事件をモチーフにした作品を書いたところ、仲間内の評価もよくて、お客様も喜んでくださったので、じゃあこの路線でやらしてもらおうと今の作風になりました。ちなみに一度だけ演出もやったのですが全然うまくいかなくて…。それで見るに見かねた日澤が名乗り出てくれて、2010年ごろから作・演出を分けた今のスタイルに落ち着きました。劇団員は現在、俳優3名、作家、演出家、制作の計6名。良く言えば少数精鋭、悪く言えば零細、非常にミニマムな劇団です。

西尾:僕は大阪府出身で、大学進学を機に東京に出ました。何作品か客演として出させていただいたのち、劇団員になりました。僕たち、今でも諸先輩方から劇団名を変えたらとよく言われるんです。甘ったるい劇団名なのに、ヒトラーとかサラエボ事件を取り扱うなど、作品の内容がかなり尖っているからでしょうね。
古川:劇団名には、誰からも好かれるような劇団でありたいという願いが込められているんです。チョコレートケーキを嫌いな人ってあまりいないですよね。甘いものが苦手な僕も、チョコレートケーキだけはおいしく食べることができるので(笑)。
■ツアーのこと
古川:ありがたいことに、『治天ノ君』を再演してほしいという声をいただき、僕たちもどこかのタイミングでやりたいと思っていました。今、トム・プロジェクトという事務所に劇団ごと所属しておりまして、力を貸していただき今回のような大規模なツアーになりました。演劇をやっている以上は、全国各地でいろんなお客様に出会いたいですし、精一杯良質な演劇をつくり、できる限りいろんな場所で公演して演劇という表現を知ってもらうことが、我々が“演劇”にできる貢献だと思っています。今回はその第一歩なので、ものすごく楽しみです。
ロシア公演は、昨年亡くなられた劇評家の村井健さんがきっかけです。日露演劇会議などを通して日本とロシアの演劇交流に尽力された方で、『熱狂』を観にきてくださって以来、すごく気に入ってくださいまして、向こうでも僕たちの劇団のことを話題にしてくださっていたようです。それで、先方から追悼公演のようなかたちで来てほしいとお声をかけていただきまして。ただ、うちの劇団単独では渡航費等は出せなくて…。それで、トム・プロジェクトさんと相談し、助成金をいただき、日露演劇会議の方にコーディネートをお願いしまして、オムスクも含めロシア3都市公演が実現しました。
西尾:題材が天皇だったので、僕たちもデリケートになっていたんですけど、初演のとき、東京ではすんなりと受け入れられたんです。この物語は、天皇の話というより天皇“家”の話で、家族の物語という側面も多いのですが、そもそも皇室を扱うことについて、他地域では褒められるのか怒られるのか…。実は昔、地方公演で上演中にヤジをとばされた経験があって。ただ、賛同だけでなく、手痛いものも含めて、いろんな反応を楽しみにしていますし、何を言ってくれてもいい、石投げてくれてもいいというぐらい強度のあるものを僕たちも作らないといけないと思っています。その観客の受取り方も含めて演劇という文化なんだといえるような作品にしたいです。
古川:演劇は、TVや映画と比べるといい意味で題材を自由に選べますし、それが小劇場のメリットだと思います。何かに囚われて天皇について書けないのではなく、むしろそのタブーに踏み込むことで、面白いお芝居がつくれたら、それはすごいことなんじゃないかと思っています。やっている側はこわごわですけど(笑)。今回、題材はチャレンジしましたが、話の核にある感情は、親子の愛だったり夫婦の愛だったり、どこにでも転がっているような、ありきたりな、でもとても大事なことであったりします。だから、題材を超えたところで、そういったことへの共感を、それぞれの公演地で―それはロシアでも(笑)―、勝ち取っていけたらと思っています。
【提携公演】
劇団チョコレートケーキ
第27回公演
『治天ノ君』
作:古川健 演出:日澤雄介
平成28年
9月21日(水)19:00
9月22日(木・祝)14:00
<公演詳細>