アイホール・アーカイブス
ハイバイ 『て』 岩井秀人 インタビュー

AI・HALL共催公演として2018年9月22日(土)~23日(日)に、ハイバイ『て』を上演します。アイホールでの本作の上演は2度目ですが、今回はハイバイ結成15周年の記念作品として登場します。
作・演出の岩井秀人さんに、作品についてお話いただきました。
■作品について

旗揚げから5年後、2008年初演の作品です。書きたい題材がなく悩んでいて思いついたのが、僕の家族のエピソードを台本にすることでした。僕の家族は暴力的な父親に抑圧されていて、それが嫌で兄弟みんなが家を離れていました。そんなバラバラな家族が、祖母の認知症の発症をきっかけに再結成しようとして、結果、前よりバラバラになってしまった。その顛末を描いたのが『て』という作品です。
タイトルを漢字にしていないのは、ただ単に身体の一部としてだけの意味になるのが嫌だったからです。ひらがなだと「何かと何かをつなぐ」という抽象的な意味になる気がしました。あと台本を書く前から祖母役の若い女優がデッサン用の手の模型を持つことは決まっていて、それもイメージの元です。
■家族について
作品のモチーフの一人である父が亡くなったので、家族の修復のようなモノは出来ていませんが、悪くもなっていないと思います。ひとつのコミュニティに悪役がいると周りは団結するように、父以外の家族は仲がいいんです。
いままでも記者さんから「お父様のことを作品で書いたり、岩井さん自身も父親になったり、そうした過程を経てお父様のことを許していってるのですね」と言われたことがありますが、その逆で「より許さなくていいんだ」と思うようになりました。世の中には、「救われるためには怒りから解き放たれなくてはいけない」という強迫観念があるようですが、僕は「父親を許さないことで、同じ轍を踏まない」と反面教師にしています。
この話の中で特に書きたかったのは、認知症になった祖母に対する長男のひどいあたり方でした。当時、兄は記憶が無くなりつつある祖母に対して「なんで忘れるんだ?」となじるような言い方で追いつめていました。僕はそんな兄を悪魔のように感じていて、その姿を面白おかしく描こうと思っていたのです。でも母は、兄と祖母の関係を全然違う風に捉えていました。兄は祖母に、働いていた母の代わりに面倒を見てもらっていて、兄弟でいちばん祖母と近い関係にあったんですね。祖母の元気だった姿をよく知っているので、現状を受け入れられずにキツイことを言ってしまっていました。そんな僕と母の捉え方の違いを表すために、同じ場面を1周目は僕、2周目は母の視点で繰り返すという構成にしました。
この作品は僕にとって箱庭療法的な作品です。母の視点で台本を書き、母を演じることで、自分の視点でしか見ていなかった問題を他者の目線から検証したので、まるで自分のセラピーのようでした。
■再演について
 ハイバイに再演が多いのは、一度お客さんに面白がられた作品をブラッシュアップしていくことを大切に思っているからです。僕は演劇の初演は上手くいってもいかなくてもそれは〈事故〉だと思っています。作る側はあれこれ予測しても、全然お客さんの反応は違って、びっくりして本番を終えるものです。だから僕の中で「初演」は〈プレビュー公演〉であり、「初演の経験をもとに練り直して再度上演するもの」を〈本当の初演〉と捉えています。今回は4回目の上演なので、もちろん以前の上演から変化する部分はありますが、かなり完成度は高くなるでしょう。
ハイバイに再演が多いのは、一度お客さんに面白がられた作品をブラッシュアップしていくことを大切に思っているからです。僕は演劇の初演は上手くいってもいかなくてもそれは〈事故〉だと思っています。作る側はあれこれ予測しても、全然お客さんの反応は違って、びっくりして本番を終えるものです。だから僕の中で「初演」は〈プレビュー公演〉であり、「初演の経験をもとに練り直して再度上演するもの」を〈本当の初演〉と捉えています。今回は4回目の上演なので、もちろん以前の上演から変化する部分はありますが、かなり完成度は高くなるでしょう。
不思議なのは、何度も再演すると、作品が自分のものではない感覚になっていくことです。上演の度にいろいろな人の人生を聞かされたからかもしれません。例えば、以前、上演後にお客さんから「先日うちも父の葬式があって」という話をされたのですが、それって実際の公演内容とは関係ないんですよね。でもそのお客さんの中で、自分の話と作品とがリンクしたのだと思います。エピソードがぴったり当てはまらなくても、見ている間に自分の人生を思い出してくれるものなのだと知って僕は驚きました。
■母役の浅野和之さんについて
浅野和之さんはハイバイに初めて出演してくださいます。“Mr.エンゲキ”みたいな人で、読売演劇大賞や紀伊国屋演劇賞などの大きな賞も受賞しながら、コミカルでちょっとおふざけの入ったような役までやれる振り幅の大きい俳優なので、舞台で初めて見た時から、機会があればぜひ出てもらいたいと考えていました。母役はコメディからシリアスまで振り幅が大きくあるので、難しいことを嬉々としてやってくれる俳優さんがいいと思っていて、引き受けてくださって感謝しています。
■「日常」を題材に
僕が戯曲を書き始めたのは、〈日常〉をベースにした岩松了さんと平田オリザさんのお芝居を観て演劇の意味を再認識したことがきっかけです。なんてことない日常に隠れる価値など、些細だけど大事なことに気づかせてもらいました。そして、とても面白かった。お客さんに、お二人の作品で感じたようなことを、僕の作品でも感じてもらえたら良いなと、その道で生きていこうと思ったんです。『て』はまさしく日常に基づいた作品で、劇団のその後の方向性を決められた上に出世作にもなったので、とても思い入れがあります。
■演劇についての思い
 僕は演劇を“悪ふざけ”の一環だと思っていて、俳優は役の人物にはなれないというのが、基本だと考えています。それは、ある演劇エッセイストが言っていた「演劇の不可能性」ということに通じていると思います。例えば、この作品では男性が母役を演じたり、祖母役を若い女性が演じていたりしますが、演劇はそんな「不可能」に挑戦しているからこそ面白いメディアなのではないでしょうか。
僕は演劇を“悪ふざけ”の一環だと思っていて、俳優は役の人物にはなれないというのが、基本だと考えています。それは、ある演劇エッセイストが言っていた「演劇の不可能性」ということに通じていると思います。例えば、この作品では男性が母役を演じたり、祖母役を若い女性が演じていたりしますが、演劇はそんな「不可能」に挑戦しているからこそ面白いメディアなのではないでしょうか。
僕自身、実は演劇を観ることは苦手で、演劇嫌いな方の気持ちも分かります。嫌われる演劇って高尚でワケがわからないものと、「みんな全力で頑張っています」感を殊更に主張してくるものとに分かれる気がして、それらが様々な人たちから観劇の機会を剥奪しているのかもしれません。ハイバイはたぶんそのどちらでもないので、演劇に苦手意識を持っている人には、特に観てほしいです!
2018年7月 大阪市内にて
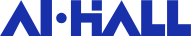




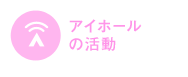


![[予約受付中]
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
令和7年度もやります!
\焼酎亭AI・HALL寄席/
関西小劇場で活躍する俳優を中心に結成された「焼酎亭一門」。
アイホールのイベントホール ホワイエに高座を設置し、カジュアルな落語会を2021年から開催しています。
役者ならではの落語。
古今東西の名曲を奏でるお囃子隊の演奏。
にぎやかで楽しいアイホール寄席へ、ぜひお気軽にお越しください
アイホール寄席初出演の方もいらっしゃいますよ~
出演者など詳細はアイホールWEBサイトまで(@ai_hall)
https://www.aihall.com/aihallyose_koi0531/
=====
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
料金:1,000円(全席自由)
※配信チケットもございます!
[予約方法]
※いずれも当日のご精算となります。
▼予約フォーム
https://torioki.confetti-web.com/form/3952/12718
▼アイホール
TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)
MAIL:info@aihall.com
=====
#焼酎亭 #アイホール寄席 #鯉 #寄席 #落語会 #落語 #役者落語 #演劇 #芝居 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)