アイホール・アーカイブス
『くだんの件』インタビュー
AI・HALL自主企画として平成28年11月11日(金)~13日(日)に、KUDAN Project『くだんの件』の上演を行います。 代表・出演の小熊ヒデジさんと作・演出の天野天街さんに、作品についてお話いただきました。

■KUDAN Projectと『くだんの件』
小熊:KUDAN Projectという団体は、海外で初演した『くだんの件』という作品が第一作目で、そのあと『真夜中の弥次さん喜多さん』、それから『美藝公』、合計で三作上演しています。それ以外に、名古屋だけですけど『百人芝居◎真夜中の弥次さん喜多さん』というのを上演しました。『くだんの件』は、関西では17年ほど前に扇町ミュージアムスクエア(OMS)で上演して以来の関西公演ですし、一番最近では、11年前に横浜で上演して以来の再演になります。作品自体の完成度、強度あるいは普遍性みたいなものは、とても強靭なものがあって、いつかまたやろうというつもりはあったんですけども、『真夜中の弥次さん喜多さん』の再演が続いたり、『美藝公』という新作をつくったりしていて、なかなか機会を持てず、今回、三重と伊丹でやろうということになって、久しぶりの上演ということになります。出来れば、今後この作品は継続して、いろんな土地で上演出来たらと思っています。

KUDAN Projectは、「少年王者舘」主宰の天野天街が作・演出をやっています。この団体は基本的に、僕と寺十吾(じつなし・さとる)の二人芝居を上演していこうというコンセプトで始まりました。僕は、名古屋の「てんぷくプロ」という劇団の所属で、寺十は横浜の「tsumazuki no ishi」という団体の代表で俳優、演出家です。ですから、それぞれがそれぞれで劇団活動をしていて、KUDAN Projectの公演があるときに集結するという感じです。それはスタッフも同じです。美術や映像、照明など主なスタッフは、初演時からずっと同じメンバーです。そういったオリジナルのメンバーで再演を繰り返しているというのが、大きな特徴かと思います。再演を続けることにより、作品の強度も増し、深まっていくという効果もあって、僕にとってはとても大事な場であるし、とても恵まれた幸せなカンパニーだというふうに考えています。
天野:この作品は僕が書いたんですけど…完成してます(笑)。21年前に書いたのですが、それから全く変えていないです。だから今回も、そのままやろうと思っています。まだ稽古は始まってないんですけども、書き直しをしようとは全く思っていません。ただ、主役となるふたり、小熊ヒデジと寺十吾というものの経年というか(笑)、歳を食ったことによって、ある意味、数限りない化学変化が起こっていくであろうと予想されます。だから、それ自体を良しとしてやっていこうと思うんですね。歳食ったからゆっくり動けとか、跳べないとかじゃなくて、いわゆる“老人力”のような考え方ですね。今あるこの状態というものの面白さを、どんどん元からあるテキスト、つまり変えない世界において、ある影響を持って相互が変化していく、という状態を希望しています。
内容についてですが……完璧に出来上がっているので話せるとお思いでしょうが、これがなかなか(笑)。結局書けても書けなくても喋れないんですね(笑)。企画書にあらすじのようなことが書いてあって、今読んだんですけど、間違ってはいないんです。この最初の三行…「夏のある日、一人の男の元に、ここでクダンを飼っていたという男が現れる。二人の謎めいた過去を巡り、物語は捩れ、迷走し、<夏>のイメージを明滅させながら分裂と増殖を繰り返す」。こういうことですね。そのなかに、どれだけの事物、世界と私というものが、連環し連鎖していろんな違ったものに変換していくか、という世界なんですね。だからもう、いろんな状態、いろんな事柄が次から次へとどんどん変質していく。その本質がどこへ向かっていくのか…本質なんて、向かうところとかベクトルとか持ちようがないんですけども、ともかくいろんなやり口を坩堝(るつぼ)のように投入してあります。これ、内容のことを言うと、いわゆるすべてがネタバレになってしまう作品でもあるんですよね。この三行で書かれていることの中に、いろいろ思いつく限りのイメージをぶちこんであるという作品なので、あらすじとか物語を言ってもどうしようもない作品です。先ほども言ったように、ディティールを語ればすべてがネタバレになってしまうという作品でもある。つまり今、語りたくないということを言い訳してるだけみたいになってますが(笑)、語りたくないんじゃなくて、どう言えばいいんだろうというような…。一応、全部連環して繋がっていくんですけど、つまり自分たちのことをいいように言うと(笑)、観る喜びに溢れ返っている作品です。ここまで自信を持っておすすめできるのは、完成しているからなので、そこがポイントですね(笑)。
小熊:部分が全体で、全体が部分、ということがある気がします。だから、一時間半くらいの上演時間なのですが、一瞬たりとも飽きることはない作品かなと思います。チラシにも「ジェットコースターで駆け抜ける」と書いてありますけれども、本当にそういうふうに、わーっと始まって終わっていく。で、おそらく観終わった方に強烈な印象を残していく。そんな作品です。
天野:あと、僕はずっと、出来る限り自分のなかのわからないことを書こうとしていたんだけど、これは「俺でも普通の芝居書けるぜ」みたいな気になって書いた作品なんです(笑)。いつもは、「夢」とか「死」という概念を扱っていても、その言葉を使いたくなかったし、使わなかった。でもこの『くだんの件』は、ハナから「夢」という文字がドワーッと出てきたり…。いつも秘めてやろうとしていたことを、わざとわかりやすいように露骨にやろうとして、より一層わからなくなっているという(笑)。そんな迷走も含めて、そういうような考えから出発したところもあります。
小熊:少年王者舘はわりと大勢出る芝居なんですけども、これは二人という少人数の芝居を初めて彼が書いて、演出した作品でもあります。
天野:だから、細かいこともいっぱい出来る(笑)。作品に出てくる登場人物はふたり、ヒトシとタロウというんですが、「人」と「牛」で“件”、「“ひと”と“うし”」=「ひとし」、そして「人」「死」=「ひとし」、ということですね。タロウというのは、「浦島太郎」であり「ミノタウロス」の部分アナグラムです。あと、「タロウ」と「ヒトシ」という字をカタカナで並べて、冒頭の文字「タ」と「ヒ」の上に線を引くと、「死」になります。すべてを分解して組み合わせると「夢」にもなりますよ。そういう文字遊びはすぐ出来ちゃうから面白くない(笑)。全部、「牛」とか、そんなところから発想して、いろんなイメージをどこまで寄せ集められるかというところもあって、言い出すときりがないんですね。それが全部でもないし。
■「くだん」に興味を持ったきっかけ
天野:僕の父は大正9年、1920年生まれなんですけど、戦地に行った

ときに同じ部隊に岡山出身の兵隊がいまして、その人が父に「“くだん”って知ってるか」という話をした。そのエピソードを父が僕に語ったんですが、何だかすごく不思議で…。その頃、“くだん”ってそんな有名な存在じゃなかったんですけど、ただある地域ではすごく語り継がれている。しかもそれが、伝説というほど古くなく、ぎりぎり明治になってからとか、第一次大戦や第二次大戦時とかで、父が聞いた話――この戦争に日本が負けて終わるということを、“くだん”が予言して、死んだという話――というのも、本当に身近な、ついこのあいだのこととして聞いたみたいです。その話を父から聞いたとき、不気味というより、すごく生々しい感触がありました。それから1990年頃に、友人の漫画家で熊本県人吉出身のとり・みきも、そういう話があったと言っていて、『くだんのアレ』という作品を連載し始めたりということもありました。このあたりだと六甲だとか、岡山、人吉とかで“くだん”の話が語り継がれているんですね。岡山は内田百閒の故郷です。彼が『件』を書いたのは明治時代ですよね。ともかく身近な感じ、すぐ横にある、というイメージでした。父が“くだん”の話を聞いたのは、昭和17年か18年頃か、災厄や戦争といった、つまり大っぴらに言っちゃいけない、ある意味タブーをまとったものが近付く、または起こっているときに、“くだん”というのはよく出現しているようです。後々、いろんな人が“くだん”のことを書いているのを見ると、やっぱりそういうことが書かれてありました。そんなところが、“くだん”に興味を持った始めです。
■今回の再演について
天野:今までも『くだんの件』の再演では、演出のやり方は変わってきているというか、過剰にするべきところは過剰にしたり、繰り返しを少し増やしたりしています。ただ言語としての、台本の文字は変えてないですね。見え方、ビジュアルはどんどん変えています。今回も、俳優のふたりを見ながら、面白ければ変えていこうと思っています。ふたりから醸し出される老臭のようなもの(笑)、破滅臭のようなものがぴったりきて、面白いアイデアが出ればどんどん取り入れていくつもりです。
_クレジットなし-1024x693.jpg)
小熊:ここ数年は、二作目にあたる『真夜中の弥次さん喜多さん』を各地で上演していて、とてもよい評判をいただいていたのですが、そのときに「『くだんの件』はいつやるんだ」「今度はいつ観られるんだ」という声を意外なほどたくさん聞きました。前々からそんな声はあったし、僕らもいつかはやろうという思いがあるにはあったので、「じゃあ、そろそろやろうかな」という気持ちが立ち上がって、天野くんを始めスタッフと話をしたのが再演のきっかけです。作中に、カウンターを飛び越えるというシーンがあるんですが、あまり先送りしていると飛び越えられなくなるので…(笑)。でも、出演している俳優、僕と寺十の状態もとてもいい状態にあると思うので、今こそかな、という思いも強くありましたね。今回は11年ぶりの再演ですけれども、それぞれが別のところで活動してきて、また集まって同じ作品に取り組むというのが、ずっと一緒にやっているのとはまた違う感触があって、それがとても面白いと思うし、それこそ化学反応みたいなことも起きる。だから、今までやってきた『くだんの件』を踏襲していくということではなく、今の状態のふたりで新しくこの作品に出会って、取り組んでいきたいというふうに思っています。言ってみれば「初めて」という言い方も出来るので、怖いなという思いもあったりしますけど、でもとても楽しみです。あと、スタッフワークも素晴らしいです。俳優より忙しいくらい(笑)。これもずっと一緒にやってきたチームワークだからこその呼吸があると思います。
天野:この作品をしたことで、得たものや変わったことなどは、あまり自覚がないんですけど…ただ、小熊ヒデジと寺十吾、このふたりのためにもっといっぱいやりたいという気持ちにはとてもなりました。スタッフたちも含めて、このふたりが喜ぶと嬉しい、みたいな。気持ち悪いですけど、こういう話(笑)。でも、そういう気持ちになってくるような幸せな集団であるということです。
■海外での反応
小熊:海外でも評判いいです(笑)。最初に言ったとおり、このカンパニーの旗揚げにあたる公演が海外だったのですが、メンバー全員が初の海外公演だったのでものすごく緊張して行ったんです。けれども、とてもすごい反応があって、どこへ行っても楽しんでいただけました。天野くんが、字幕というものを使わないので、俳優が現地語の台詞が書かれたフリップボードみたいなものを出していくんですね。要はライブなので、スライドで字幕を読んでもらうのを嫌って、現地へ行ってからそういう方法を発明したんですが、それがすごく効果的でした。今まで字幕というものが、台詞の情報を伝えるだけのものだったのが、形になることでそれを小道具のように扱えて、字幕すら表現の一部に取り込んでいった。それも高い評価を得たことのひとつでした。そんなふうに、みんな最初はどうなることかというような思いで旗揚げして、海外へ行って、それがとても手応えのある公演になったということが、今までKUDAN Projectが続いている大きな理由になってるのかなと思います。KUDAN Projectでつくっている作品、天野天街の作品が、言葉以外のところで十分伝わる作品だし、文化とかそういったものを超えた、もっと普遍的なものを持った作品だということを改めて認識出来た、ということも大きなことだったと思います。
 天野:海外での反応は、本質的なところでは日本と変わらないんですけども、この作品は日本語でしか出来ない洒落を、相当なレベルで使っている。そういうのは全然ウケないですね。ただ、海外の場合、そういうのを別な形に変換したり、やり口を変えて見せたりしますね。例えば、「にかいのうし」という言葉があります。二階で飼っていた牛…「二階の牛(にかいのうし)」が、二階から突き落とされて脳死状態になる…「二回脳死(にかいのうし)」というイメージに繋がっていくわけですが、そういうのは伝わりません(笑)。ただ、「七夕」という文字を出して、それをふっとひっくり返すと「死」という字になる、というのがあるんですが、中国圏でそういうのをやるとものすごくウケたりします。ヨーロッパ圏、英語圏では無理なんですけど、漢字圏ではそういうやり方があります。日本語だけの言葉の洒落では全く反応がないので、別なことで変換しないといけない。ビジュアルですね。
天野:海外での反応は、本質的なところでは日本と変わらないんですけども、この作品は日本語でしか出来ない洒落を、相当なレベルで使っている。そういうのは全然ウケないですね。ただ、海外の場合、そういうのを別な形に変換したり、やり口を変えて見せたりしますね。例えば、「にかいのうし」という言葉があります。二階で飼っていた牛…「二階の牛(にかいのうし)」が、二階から突き落とされて脳死状態になる…「二回脳死(にかいのうし)」というイメージに繋がっていくわけですが、そういうのは伝わりません(笑)。ただ、「七夕」という文字を出して、それをふっとひっくり返すと「死」という字になる、というのがあるんですが、中国圏でそういうのをやるとものすごくウケたりします。ヨーロッパ圏、英語圏では無理なんですけど、漢字圏ではそういうやり方があります。日本語だけの言葉の洒落では全く反応がないので、別なことで変換しないといけない。ビジュアルですね。
■再演を繰り返すということ
小熊:再演をするたびに、台詞が変わるわけではないし、毎回、演出的に大きな変化があるわけではないんですけども、俳優同士の感触というか手触りというか、そういうのは違ってきますし、それぞれの経験を経てまた出会って、また一緒に芝居をするということで、微妙に変わってくることはありますね。それがやっぱり新鮮だし、嬉しい。最近は再演を繰り返すカンパニーも増えてきているとは思うんですが、まだまだやっぱり小劇場は初演で終わりというところが圧倒的に多い。繰り返すというのはとても大事だと思いましたし、すごい体験が出来ます。何回も同じ作品をやっていて、お互いのコンディションがとてもいいときに公演をすると、台詞も身体の中に入っているし、もう細胞の一部みたいになってくるんですよ。この作品だと僕は「ヒトシ」という役をやるんですけど、そうすると、自分の半歩先にヒトシがいるんですね。僕がそのあとをついて行くんです。わかりにくいですよね(笑)。でもそんな感覚になるんです。自分がその舞台の客席の一番前の隅っこで、自分の芝居を観ているような感覚になるんです。勝手に芝居が進んでいくような…。この『くだんの件』とか、『真夜中の弥次さん喜多さん』では、今までしたことのない、そんな体験をしました。自分でもびっくりしました。本当に役者冥利につきるというか…
天野:単に酸欠に陥って、脳死状態に近付いた…
小熊:のかもしれないです(笑)。
天野:幽体離脱みたいな(笑)。ただ、老残を絡げて、枯れてのんびりして、上演時間が延びる…というようなことは絶対にやらないようにしています。前回と同じテキストなんだけど、軋みとか捩じれとかブレみたいなもの、うねりみたいなものが、肉体の様子が変わったことによって生まれればいいな。全く同じテキストで同じことをやっているのに、前とは違う時間の流れになって、結局、着地点は一時間半でスポンと終わると、そういうような形に仕上げたいと思っています。
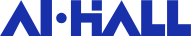




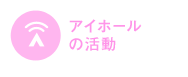


![[土曜日のワ―クショップ]
本日4月19日(土)、土曜日のワークショップ 「ストレッチ・エクササイズ」初回でした!
足や腰、背中を意識しながらゆっくり呼吸を整えながら伸ばしていきます。自分のペースでゆっくり身体と向き合える人気講座です。
現在全ての回がキャンセル待ちですが、また2期、3期とご案内しますのでぜひご参加ください。
#土曜日のワークショップ #ストレッチエクササイズ #ボヴェ太郎 #ストレッチ #エクササイズ #姿勢改善 #肩凝り #腰痛 #和室 #アイホール #東リいたみホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)