アイホール・アーカイブス
烏丸ストロークロック『まほろばの景 2020』 柳沼昭徳インタビュー
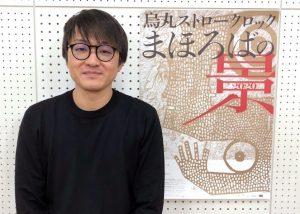
AI・HALL共催公演として2020年1月25日(土)~27日(月)に、烏丸ストロークロック『まほろばの景 2020』を上演します。
2018年に長編作品として東京・京都で上演し、反響を呼んだ作品を、各地での取材とフィールドワークを重ねて新たに生まれ変わらせた話題作です。
烏丸ストロークロック主宰であり、作・演出の柳沼昭徳さんに、作品の見どころや創作の背景についてなどお話しいただきました。
■創作のきっかけ
2017年、初演の半年前ぐらいに、仙台で滞在製作をしているんですが、『まほろばの景』の創作を試みたのはそこがスタートでした。震災後、テレビやインターネット、映像や手記などで、震災のことを目にする機会は多いですが、そうやって情報はどんどん目の前にやってくるんだけど、その情報と自分の心との距離があり、自分の中で「あのとき何もしなかった」という、自身への呵責みたいな気持ちがずっとありました。
そこで、いつか現地に行きたいと思っていて、とある作品を作るときにお願いして東北に取材に行ったことが創作の始まりでした。 直接関係ない人間が震災を扱っていいのかという逡巡はもちろん今もあるし、その当時もありましたが、いちばん最初の核になったのは、2017年の7月に、『まほろばの景』の短編作を作ったときの取材で出会った方から聞いたお話です。
直接関係ない人間が震災を扱っていいのかという逡巡はもちろん今もあるし、その当時もありましたが、いちばん最初の核になったのは、2017年の7月に、『まほろばの景』の短編作を作ったときの取材で出会った方から聞いたお話です。
仙台市の沿岸部に津波で流された集落がいくつかあるんですが、その集落に住んでいた方に、震災によって失われた生活や風習について聞いたお話の中で、「井戸の話」がすごく印象的でした。『まほろばの景』の中でもそのエピソードを始まりにしています。
津波で流されたあるおじいさんの家があった場所に向かったら、もうそこにはコンクリートの井戸しか残っていなかった。その井戸を前にして、おじいさんが「夢みたいだな」っておっしゃったんですって。「夢みたい」っていうのは、普通ポジティブなときに出てくる言葉ですよね。「信じられない」っていう意味で使われていたというのは、すごく理解できるんですが、それがこういう悲痛な状態で「夢みたい」って呟かれたという話が、すごく印象に残っていて、自分の中に響きました。その「夢みたい」という言葉から、この作品は始まっていきます。 初演の東京公演の時に聞いた感想の中で、「都会に突如現れた祭壇」ということを仰っていたお客さんがいて。それを聞いて、そう受け取ってもらえるものを僕たちは創っていたんだなということに気付いたんですね。じゃあこれを、今度はもっとそれぞれの観客の人たちの想いと舞台が、もうちょっと深く関係を持てるような作品にしたいねと話しました。表層的なことではなくて、日本人の根っこに流れるものを汲み取りたいと思うところから再創作が始まっています。
初演の東京公演の時に聞いた感想の中で、「都会に突如現れた祭壇」ということを仰っていたお客さんがいて。それを聞いて、そう受け取ってもらえるものを僕たちは創っていたんだなということに気付いたんですね。じゃあこれを、今度はもっとそれぞれの観客の人たちの想いと舞台が、もうちょっと深く関係を持てるような作品にしたいねと話しました。表層的なことではなくて、日本人の根っこに流れるものを汲み取りたいと思うところから再創作が始まっています。
■『まほろばの景』について
今回の作品は東日本大震災で仙台の実家が津波で流された男性が主人公です。
舞台は主に山の中です。震災で自分自身も家族も無事だった男が、その後、震災後を生きている中で抱える屈託を、山を登ってる中でいろんな人たちと出会いながら、自分の過去を反芻していくというお話です。
震災そのものがテーマということではなくて、「震災」というものを起点にして、それ以降、人々の中にどのような心の変化があったのか、どう価値観が変化していったのか、また、震災以降、社会は変わったけれど、社会と個人の乖離みたいなものを解消していくにはどうしたらいいのか、ということを描いた作品になります。

この物語は“福村洋輔”という主人公のことを描くんですが、山を登っていく中で主人公と様々な人たちが交流し、彼以外の様々な人たちの記憶やイメージが挿入されていくことで、ひとりの男の経験、記憶も共有していくという見せ方になるのが、再創作にあたっての大きな変化じゃないかなと思っています。
初演の時は、劇中で登場する神楽もちょっと振りをお芝居に取り入れるぐらいのレベルだったのですが、今回、神楽というものを勉強し直して、集団で共通している身体を持つことの強度ってすごいなと気付きました。そこで、男が語る等身大的な個の話を全員が語るという方向に持っていこうと思っているんです。
個人の経験とか記憶を、複数人が共有するということは、まず現実では絶対に起こりえないことです。でも、そもそも俳優には他人の書いた言葉を自身と混ぜて喋るということが、ひとつ役割としてあると思います。仲介者、媒介者として俳優がいて、誰かの思いをそれぞれが演じるとかではなくて、混ざっているという状態です。それが、集団の力だったり、コミュニティの力だったりすると思います。
■神楽と震災
今回の再創作では日本人の身体や、神楽というものが持っている文脈も汲み取ったうえで、それを舞台全体に組み込むことは出来ないかなという試みをしています。神楽を古典芸能として舞台に載せるというだけではなくて、古の身体だったり、その精神性、宗教性というものが今と繋がってるようにお見せできるようにしています。
神楽っていうものは、遡ってみると、農産物の収穫だったり海産物を獲ることだったり人間ではコントロールできないことを神様に頼んでお願いしようというところが根本にあると思うんです。そういう意味で、震災と神楽を結びつけるのにあたり、「信仰」というファクターは大きいと思います。
「都会に現れた祭壇」という言葉にもある通り、震災のあと、日本人がもう少し何かしらの信仰心を持っていれば、救われた人はもっと多かったんじゃないかという仮説を立てました。人間の力や個々の精神ではコントロールできないレベルのことが起こってるわけですから、それを解消はできなくても、まず出来事を受け入れるというプロセスの中には、祈ることはすごく重要になってくると思います。お釈迦さんでもキリストさんでも何でもいいんですけど、何か自分じゃない存在に心をあずけるということができれば、少しは屈託を軽減することができるんじゃないでしょうか。
神楽は、踊ることで「これから田植えをするので神様降りてきてください」と五穀豊穣を祈って、神様をおろしてくるわけです。そして収穫が終わったらありがとうございました、山にお帰りくださいって返すという祈りなんですよね。
-300x200.jpg)
初演の時は、神楽を舞としてやってたんですけど、いろいろ見聞きしていくうちに、これは祈りなんだなと思いました。舞手が観客も含めてトランス状態になっていく力強さがあり、やはり信仰というものがないとそこには至らないんです。“ショー”ではなくて“プレイ”なんだなと思った瞬間でした。だから我々が再創作するときには、“ショー”ではなく“祈り”としての要素、その側面をもっと強くしていきたいという思いに至りました。
震災があって、人の弱さ、脆さみたいなものをすごくたくさん色んなところで目にします。神楽を見ていると、やはりかつて同じように、突如日照りが続くとか、いなごの大群が襲ってくるとか、ご飯が食べられなくなる危険が何の規則性もなくやってくる。それこそ当時も地震もあっただろうし、津波もあっただろうし人は死ぬ。(そうやって前触れもなくやってくる)全然意味が分からないものと、どうやって人が向き合うのかという時に、絶対に抗えないということが分かっているうえで、「じゃあもう祈るしかない」という状態で繰り広げられる行為を見ると、すごく人間って美しいなと思います。
神楽は多岐に渡りすぎて、種目ごとに同じように見えて全然違ったりする、研究者泣かせの芸能だと思うんです。だからこそ流行り廃り関係なく続いてこれたんだろうなと思うし、強度がすごいです。我々も見習うところがあるなと思いますね。
(2019年12月大阪市内)
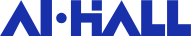




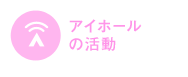


![【チケット発売】5月31日(土)10:00~
地域公共劇場連携事業
「りすん 2025 edition」リ・クリエイションツアー
原作:諏訪哲史
脚色:天野天街
演出:小熊ヒデジ+天野天街
📅日時
8月2日(土)14:00/18:30★
8月3日(日)14:00
★アフタートーク
諏訪哲史、小熊ヒデジ、出演者
(司会進行)小堀純
🎫チケット料金
[整理番号付き全席自由席]
一般 3,800円
伊丹市民割 3,300円
U25 2,500円
高校生以下 1,500円
【チケット取扱い】
◎アイホール
TEL072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)
◎チケットぴあ
https://t.pia.jp/(Pコード:533-524)
◎カンフェティ
http://confetti-web.com/@/listen2025_aihall
TEL050-3092-0051(平日10:00-17:00)
【お問い合わせ】
アイホール(9:00~22:00/火曜休館)
https://www.aihall.com/
TEL 072-782-2000
MAIL info@aihall.com
#りすん #リクリエイション #ツアー #諏訪哲史 #天野天街 #小熊ヒデジ #加藤玲那 #菅沼翔也 #宮璃アリ #演劇 #芝居 #小説 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)