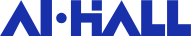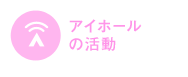アイホール・アーカイブス
現代演劇レトロスペクティヴAI・HALL+内藤裕敬『二十世紀の退屈男』
内藤裕敬インタビュー
 現代演劇レトロスペクティヴは、時代を画した現代演劇作品を関西を中心に活躍する演劇人によって上演する企画です。今回、南河内万歳一座の内藤裕敬さんがアイホールとタッグを組み、自身の初期代表作を上演します。公演に先駆け、内藤さんにお話を伺いました。
現代演劇レトロスペクティヴは、時代を画した現代演劇作品を関西を中心に活躍する演劇人によって上演する企画です。今回、南河内万歳一座の内藤裕敬さんがアイホールとタッグを組み、自身の初期代表作を上演します。公演に先駆け、内藤さんにお話を伺いました。
 ■「ザ・昭和」な作品を若い人たちとつくる
■「ザ・昭和」な作品を若い人たちとつくる
『二十世紀の退屈男』は、六畳一間シリーズの第3作目で、初演が1987年、約30年前です。その後、南河内万歳一座では何度か再演をしています。劇団の作品を、全キャストオーディションで上演するのは今回が初めてです。「万歳の芝居は万歳じゃないとできないんじゃないか」と思われる人もいるかもしれませんが、「そんなことないよ」というようにしたいと思っています。また、「ザ・昭和」という感じの作品なので、上演するにあたっての賞味期限が切れていないか、すごく気になっています。かといって、現代風にアレンジするのはよくないだろうとも思い、「若い人たちが、今、この作品をやるとどうなるのだろう」ということを、稽古をしながら慎重に見守っています。
舞台は青年が暮らす六畳一間。その部屋には、都市に出てきたが、夢叶わず都市から去っていった、かつての住人たちのさまざまな痕跡が傷やシミとして残っています。その痕跡たちが一気に騒ぎ出し、そこで暮らす男の孤独をそそのかすというのがオープニングです。そこに、青年宛ではない手紙が間違えて配達されます。配達した人を探すために彼が外出しようとすると、その六畳一間にかつて暮らしていた人たちが仕事や遊びから帰ってきて、みんな「ここは自分の部屋だ」と主張します。物語はその部屋の持ち主の決め手を見つけるべく展開していき、実はいわくつきの部屋だということも歴代の住人たちの証言でわかります。都市の六畳一間を舞台に、過去にそこで暮らしていた人たちを巻き込み、青年が孤独と青春の焦燥感に対してもがく一日の物語です。
だから、主人公の持つ孤独を共感できたり、イメージをリアルに感じることができないと、この作品を立ち上げていくのが難しい。稽古が始まって最初の一週間は、台本を読んだり立ったりしながら、出演者にそのことを徹底的に言いました。みなさん違和感なく理解しています。
今、大阪芸術大学で授業を担当しているんですが、学生と向き合うと、もしかしたら僕らの頃より貧乏かもしれないと感じます。さすがに今は六畳一間の木造ボロアパートはないですが、学生の生活そのものは貧乏でお金に困っています。僕自身、若者の現状は今も昔もあまり変わってない印象を持っていますので、主人公の青年が持つ、青春の焦燥感と孤独感をしっかりとフューチャーして立ち上げれば、現代風なアレンジではなくても、今にも通じるものができるのではないかと思っています。リライトは少ししますが、作品全体の昭和的なディティールは変えません。携帯電話も出てきません。“手紙”という頼りない伝達手段が、物語や登場する人物の関係をややこしくしていきます。そのアナログさを、一つの創造性として担保しておきたいと思っています。
■青春の焦燥感と苛立ちを描いた作品 この作品は僕が27、8歳のときに書いたもので、二つの詩をモチーフにして作ったことを改めて思い出しました。それは、ルイ・アラゴンの「青春の砂のなんと早く/指の間から/こぼれ落ちることか」という詩と、石川啄木の『一握の砂』にある「いのちなき砂のかなしさよ/さらさらと/握れば指のあひだより落つ」という詩です。もう手の中に残っていないと感じた青春の焦燥感と、「二十代はこんなはずじゃなかった」という僕自身の思いが、『二十世紀の退屈男』のスタートになっています。
この作品は僕が27、8歳のときに書いたもので、二つの詩をモチーフにして作ったことを改めて思い出しました。それは、ルイ・アラゴンの「青春の砂のなんと早く/指の間から/こぼれ落ちることか」という詩と、石川啄木の『一握の砂』にある「いのちなき砂のかなしさよ/さらさらと/握れば指のあひだより落つ」という詩です。もう手の中に残っていないと感じた青春の焦燥感と、「二十代はこんなはずじゃなかった」という僕自身の思いが、『二十世紀の退屈男』のスタートになっています。
二十代前半は「これから様々な出会いがあって、いろんな体験をして、何かが大きくなっていく」という未知なる期待があったのに、半ばになって「こんなはずじゃなかった」と首を傾けはじめる。そして二十代後半になると「このまま三十になっちゃうの? こんなことでいいんだろうか」と思い始め、どんどん自分の可能性が剥がれ、やせ細っていくのではないかという苛立ちと、輝かしい時間が何もないまま終わっていくのではないかという青春に対する焦燥感みたいなものが生まれる。都市に出てきて、自分は前に向かって踏み出そうと頑張ったのに、ハッと気がつくとポツンと孤独で、友人が多くできたわけでもなく、仕事が上手くいっているわけでもなく、何かを探し当てたわけでもなく、ものすごく退屈な二十代の中にいる自分に気づく。当時の僕は、自分が傷ついたり人を傷つけたりすることが二十代の証しになるような気がして、「どうせ孤独な退屈のままで何もないんだったら、悪いことでも起きたほうがまだマシだ」という感覚になっていました。主人公には、そういった僕自身が反映されています。
また、自身への課題として「長台詞を書くぞ」という覚悟で書いた作品でもあります。当時、長台詞が書けないことで悩んでいた時期でした。唐十郎さんと知り合って三年目くらいだったんですが、唐さんの舞台は、まぁ見事な長台詞が並ぶんですよね。それで「唐さんのように三幕で三時間という構成はできないです。長台詞が書けなくて、会話を転がしていって、たまに書いても五行くらいなんです」と唐さんに話すと、「無理して書かなくてもいいんだ。ただ、長い台詞というのは文学的な要素が入るので、自分の劇文体の文学性と向き合わなくてはいけないね」とおっしゃってくれました。そんなこともあって、文学的に長台詞をやってみようと思って書いた作品なので、いま読むと「文学青年をやり過ぎているだろ」と鼻につくところがあります。そこを今回、少し手直ししようか悩んでいます。ちなみに三幕構成については、唐さんに「三幕にならなくてもいいから、“果てしない一幕”を書けばいいんだよ」と言われました(笑)。ここ十年ぐらいで「果てしない一幕」を書くということに向き合って芝居をやっているなという気がしています。
■出演者について
出演者は、60人以上の中から全員オーディションで選抜しました。オーディションには力量的にもっと上手い役者もいました。でも、この作品ですし、下手でも野心的で威勢の良い役者がいい、暴力的に、なしくずし的に舞台を成立させるくらいの筋力を持っている役者がいいと思い、その基準で選びました。そういう意味では、みなさん稽古場でその能力を発揮してくれています。オーディションで採用した、活きのいい俳優がいるので、初演時に新人劇団員に「君たちは“老人たち”で」とぞんざいに割り振ったシーンをリライトし、出演者ひとりひとりが活躍できる台詞を書きたいと思っています。
稽古をしていると、役者たちは、舞台上で何かを発散したいという思いを持っているけど、いつも不完全燃焼で、何か手で掴めそうなものがいつも届かずに終わってしまっているという感覚を繰り返してきたのではないかと感じます。だから今回、ダイナミックに暴れることで、何か新しい自分のハードルを一つ越えてやろうという気概を持っている。みんな非常に前向きですから、その良い面を演出で引き出せば、初演とはまた違う熱量を持った作品を発表できると思っています。もちろん、作品の匂いや温度は変えるつもりはありません。
■いま、この作品を上演すること
今は、2.5次元演劇が流行ったり、プロジェクションマッピングといった映像的なものも芝居の中で多用されていますよね。でも、僕はそんなことはまったく考えてなくて、とにかく人間が、生き物としてどんな表現ができるかを必死にやってきました。そこが一番違うなとすごく痛感します。舞台を観る観客のニーズというか、観客が感性として舞台に求めているものが、ものすごく変わっちゃったのかなとも感じています。かつては、商業的なものとか、お客さんがいっぱい入っているものを観たとき、演劇的には食い足りないと感じても、「演劇っておもしろい。もっと他のものを見てみよう」というお客さんが 一人でも増えるならいいんじゃないかと思っていました。けれど、2.5次元の舞台を観た観客の感想を読んでいると、それも期待できないんじゃないかと個人的に思っています。あそこに演劇の観客が育つ環境は無い気がしていて。逆に、今回のようなお芝居の中から新しいムーブメントを起こさないといけないという思いが強くなりました。演劇の新しいことや、舞台で成立しうる劇的な瞬間にしがみついて具現化しないと、観客は観てくれないんじゃないかと思っています。だから、暴れ回っていた当時を思い出しながら稽古を進めています。
一人でも増えるならいいんじゃないかと思っていました。けれど、2.5次元の舞台を観た観客の感想を読んでいると、それも期待できないんじゃないかと個人的に思っています。あそこに演劇の観客が育つ環境は無い気がしていて。逆に、今回のようなお芝居の中から新しいムーブメントを起こさないといけないという思いが強くなりました。演劇の新しいことや、舞台で成立しうる劇的な瞬間にしがみついて具現化しないと、観客は観てくれないんじゃないかと思っています。だから、暴れ回っていた当時を思い出しながら稽古を進めています。
観客のみなさんは、ご覧いただいたときに、「へー、昔は、こんなことやっていたんだ」という驚きや面白さがあるかもしれません。あるいは、「これは古い」と思われるのかもしれませんし、「いやむしろ新しい」と思われるかもしれません。いま、この作品を上演することで、観客のみなさんがどう感じられるのかについても僕は興味を持っています。ぜひ、ご覧いただければと思います。
Q.「ザ・ 昭和」とは、具体的にはどういったところですか?
「西日が差す」「六畳一間」「木造モルタルのアパート」という作品に出てくるワードが、すでに“昭和”ですよね。西日があたる壁際に服をかけると色がくすむとか、タンスを置くと湿気がひどくて壁にカビが生えているとか、狭い六畳一間を有効活用するために押し入れの中に布団を敷いてベッド代わりにしているといった生活をしていることもです。そもそも六畳一間が、自分の青春の生活空間のすべてだということ自体が、ものすごく“昭和”な匂いを発していると思います。何が「昭和的」かという感覚は人によって違います。ただ、僕は、昭和という時代は即興的だったのではないかと思っています。戦争があって、戦後に急激な復興を遂げ、オリンピックや万博があって、高度成長期のピークを迎えるという、ものすごく駆け足で発展した時代。ボンネットバスが走れば埃で道路沿いの家の窓が真っ白になっちゃうとか、雨が降れば道路がぐちゃぐちゃになって長靴を履いて会社に行っていた時期から、東京オリンピックと大阪万博の開催で、あっという間にインフラが整備され、舗装道路ができ、いろんなものがきれいになっていく時期まで、ほんの数十年ですよね。一方で、高度成長期の発展が「みんな右へ倣え」でなく、取り残されたような木造モルタルの文化住宅もいっぱいあった。近代と前近代がごちゃまぜに存在しているようで、それが面白いアンサンブルになっていた。その、デコボコした感じの面白さがあった時代なんじゃないかと思っています。
Q.この作品を選定したのは、アイホールと内藤さんのどちらですか?
現代演劇レトロスペクティヴでは、唐十郎さんや寺山修司さんなど、既にいろいろな作家の作品をされているので、何を上演するかはアイホールと会ってだいぶ話したんです。僕としては、じっくり構えるなら、秋浜悟史さんか清水邦夫さんの作品だと思ったんだけど、既に演出されていますし、長谷川伸あたりをやろうかという話になりましたけど、それも「現代演劇」という企画の枠としてどうかという話になって・・・。結果的に、自分の作品をやるかとなりました。
それで、どうせ自分の作品をするなら、いまの若い人と組みたいと伝えました。今回、南河内万歳一座からは一人も出ていません。これは僕自身や劇団にとってもひとつの課題なんですが、再演をやろうにも劇団員の平均年齢が上がっているので、若い人をオーディションで選んで劇団員が脇を固めないとできない作品がいっぱいあるんです。今回、若い人とちゃんとコミュニケーションを取って、一本、面白い作品を発表できたなら、今後の南河内万歳一座でもその試みをするきっかけになるとも思っています。
『二十世紀の退屈男』
作・演出/内藤裕敬
平成30年
2月22日(木) 19:30
2月23日(金) 19:30
2月24日(土) 14:00/18:00
2月25日(日) 14:00
2月26日(月) 14:00