アイホール・アーカイブス
オフィスコットーネ 綿貫凜インタビュー

アイホールでは、2019年5月24日~27日に、オフィスコットーネプロデュース 大竹野正典没後10年記念公演 第3弾として、改訂版『埒もなく汚れなく』『山の声』の連続上演を行います。当館ディレクターの岩崎正裕が、コットーネプロデューサーの綿貫凜さんにお話を伺いました。
■劇作家・大竹野正典との出会い
岩崎:綿貫さんはオフィスコットーネのプロデューサーとして、たくさんの大竹野正典さんの戯曲を上演されてきました。大竹野さんの活動の場は主に関西で、東京ではあまり活動されていらっしゃらなかったと記憶しています。どういう出会いがあって、こうした取り組みをされているのでしょうか? 綿貫:私が初めて大竹野さんの戯曲と出会ったのは2012年に、二人芝居をするために台本を探していた時期です。なかなか面白いホンに出会えてなくて、ふと、知人が二人芝居をやっていたことを思い出して連絡したんです。それが『山の声』だった。根掘り葉掘り聞いてすぐに台本を送ってもらって、電車の中で最後まで読みました。そうしたら、すごく面白くて、「これやろう」と即決しました。こんな面白い作家がいるんだと驚きました。すでに故人で戯曲集があると聞いたので、最初は70歳ぐらいのおじいさんだと思っていました(笑)。そのあと、『大竹野正典劇集成Ⅰ』をインターネットで買い、全部読んだんです。どれも面白くて、これは続けてやりたいと思いました。コットーネで大竹野作品を最初に上演したのが『山の声』で、30人ぐらいのスペースで、関西弁ができなかったので標準語でやらせてもらいました。
綿貫:私が初めて大竹野さんの戯曲と出会ったのは2012年に、二人芝居をするために台本を探していた時期です。なかなか面白いホンに出会えてなくて、ふと、知人が二人芝居をやっていたことを思い出して連絡したんです。それが『山の声』だった。根掘り葉掘り聞いてすぐに台本を送ってもらって、電車の中で最後まで読みました。そうしたら、すごく面白くて、「これやろう」と即決しました。こんな面白い作家がいるんだと驚きました。すでに故人で戯曲集があると聞いたので、最初は70歳ぐらいのおじいさんだと思っていました(笑)。そのあと、『大竹野正典劇集成Ⅰ』をインターネットで買い、全部読んだんです。どれも面白くて、これは続けてやりたいと思いました。コットーネで大竹野作品を最初に上演したのが『山の声』で、30人ぐらいのスペースで、関西弁ができなかったので標準語でやらせてもらいました。
岩崎:それ以降、東京における大竹野正典の再評価が高まっているのが現在ですよね。
綿貫:ただ、2012年から数年は誰も振り向いてくれなかったです。「くじら企画」(大竹野正典主宰)は、東京ではまったく公演をやってらっしゃらなくて、大竹野さんのことを知っている人は誰もいなかった。2014年に上演した『海のホタル』の評判が良く、劇評家や新聞社の人がたくさん来てくれて、「面白いけど、この人は誰なの?」とやっと興味をもってもらえました。そして、大竹野正典という劇作家がいて、若くして死んだけど面白いねという感じになっていきました。
岩崎:大竹野さんは関西でも“いぶし銀”の光り方でした。彼は建築現場でコンクリートの技師をされていて、私が工事現場で旗振りのアルバイトをしていた時期にお会いしているんです。「よぉっ!」とか、「今日、コンクリート打つの?」とか言って。同世代でお互い意識はしていたけど、ご一緒する機会はありませんでした。だから、彼の死がすごく衝撃でした。それからこんなに時間が経ち、大竹野さんの作品が東京で脚光を浴びていることに、今、とても羨望のまなざしで眺めております。
綿貫:東京に出てきた関西の人に「大竹野さんを知ってますか?」と聞くと、「知らない」とか「名前を聞いたことはあるけど作品は観たことがない」という人が多い。こんなに面白いものを書いているのになぜみんな知らないのだろう、どうやったらこんな才能が埋もれたままになるのかと気になったのがスタートです。
■改訂版『埒もなく汚れなく』で描く大竹野像
岩崎:今回は、大竹野さんの人間関係に焦点を当てつつ、人生を描いていくのですか? 綿貫:作・演出の瀬戸山美咲さん(ミナモザ)は、名もない人物を取材を通じて描くことを得意にされている作家です。2016年の初演のときに、大竹野正典さんという面白い作家がいるので、その人のことを取材して書いてほしいと依頼しました。それで、「くじら企画」の面々、奥さんの小寿枝さんや娘さんなどに話を聞きました。初演版では、大竹野さんが奥さんと出会い結婚し『山の声』を書いて亡くなるところまでを描いたのですが、私も瀬戸山さんも大竹野さんには直接会ったことがありません。だから、私は主に作品からイメージして、瀬戸山さんは奥さんに取材をしたことで、旦那でありダメな人であり作家として才能のある人という、“奥さんの目線からみた大竹野像”が描かれました。今回の改訂版ではその6割ほどを残し、他はカットして新しいエピソードを挿入します。実は、『山の声』を書きあげる前の45歳ごろと、そのもっと前の35歳ぐらいのときにホンが書けなくなっている。今回、スランプの時期を新たに挿入することで、作家が書けなくなるとはどういうことなのかを分析しながら、大竹野さん像に迫っていくことにしました。大竹野さんは演劇を仕事にしていないわけで、そのなかで「次はどういうのを書くの?」というみんなからの期待や、前より面白いものを書かなくちゃいけないという重圧に耐えられなくなったのではないかと仮説を立てています。今回、改めて取材をして、亡くなって10年経ち、みんなの中で美化されてきている、だんだん美しい記憶にすり替わってきている部分も多いと感じました。素晴らしいだけじゃない、つらい部分もあるんだということを描きたい。
綿貫:作・演出の瀬戸山美咲さん(ミナモザ)は、名もない人物を取材を通じて描くことを得意にされている作家です。2016年の初演のときに、大竹野正典さんという面白い作家がいるので、その人のことを取材して書いてほしいと依頼しました。それで、「くじら企画」の面々、奥さんの小寿枝さんや娘さんなどに話を聞きました。初演版では、大竹野さんが奥さんと出会い結婚し『山の声』を書いて亡くなるところまでを描いたのですが、私も瀬戸山さんも大竹野さんには直接会ったことがありません。だから、私は主に作品からイメージして、瀬戸山さんは奥さんに取材をしたことで、旦那でありダメな人であり作家として才能のある人という、“奥さんの目線からみた大竹野像”が描かれました。今回の改訂版ではその6割ほどを残し、他はカットして新しいエピソードを挿入します。実は、『山の声』を書きあげる前の45歳ごろと、そのもっと前の35歳ぐらいのときにホンが書けなくなっている。今回、スランプの時期を新たに挿入することで、作家が書けなくなるとはどういうことなのかを分析しながら、大竹野さん像に迫っていくことにしました。大竹野さんは演劇を仕事にしていないわけで、そのなかで「次はどういうのを書くの?」というみんなからの期待や、前より面白いものを書かなくちゃいけないという重圧に耐えられなくなったのではないかと仮説を立てています。今回、改めて取材をして、亡くなって10年経ち、みんなの中で美化されてきている、だんだん美しい記憶にすり替わってきている部分も多いと感じました。素晴らしいだけじゃない、つらい部分もあるんだということを描きたい。
岩崎:関西では、大竹野さんに実際に会った人が多いと思います。近いところにいた人は、自分の記憶をたどりながら見てしまうと思います。東京だと虚構化できていたことが、関西では、観客側も頭を整理しないと観ることができないかもしれないですね。逆に、今の20代といった大竹野さんのことを知らない人たちは、新しい作家と出会う体験をするわけですね。
■「表現」と「食べていくこと」と「矛盾」と
綿貫:タイトルの「埒もなく」は、私が大竹野さんのエッセイのなかで一番好きな「埒の無いこと」(『劇集成Ⅱ』所収)にある一節、「芝居は埒の無い発明である」からいただきました。東京で演劇をしていると、演劇を仕事にしてお金に変えていくということにガツガツしちゃうんですよね。私自身も仕事をしていくなかで、自分がやっていることをたまに見失うことがあるんです。でも、この文章を読んだときに、ああ、こういう考え方でいいんだと救われるんです。 岩崎:大竹野さんは「売れる」ということを考えてなかったと思います。「なんで芝居って一年前に劇場を押さえないといけないんだろう、これをやりたいと思ったら二週間前に押さえられる劇場は無いのか」みたいなことをおっしゃっていて、芝居の即時性にすごく拘っていらした感覚があります。観客動員については考えていたけど、収支トントンぐらいで俺たちの表現はいいんだと思っていたように感じます。関西にはそういう人が意外と多いんです。昔、宮沢賢治とかが考えていた「農民芸術」の運動がありますよね。農業をやりながら、わたしたちは新しい表現・芸術活動をするんだという考え方。同じような立脚点の人が、地域にはいると思います。そういった考え方を大竹野さんを通じて東京の人たちが触れるのはいい機会かもしれないです。
岩崎:大竹野さんは「売れる」ということを考えてなかったと思います。「なんで芝居って一年前に劇場を押さえないといけないんだろう、これをやりたいと思ったら二週間前に押さえられる劇場は無いのか」みたいなことをおっしゃっていて、芝居の即時性にすごく拘っていらした感覚があります。観客動員については考えていたけど、収支トントンぐらいで俺たちの表現はいいんだと思っていたように感じます。関西にはそういう人が意外と多いんです。昔、宮沢賢治とかが考えていた「農民芸術」の運動がありますよね。農業をやりながら、わたしたちは新しい表現・芸術活動をするんだという考え方。同じような立脚点の人が、地域にはいると思います。そういった考え方を大竹野さんを通じて東京の人たちが触れるのはいい機会かもしれないです。
綿貫:東京で生まれて育っている私からするとすごく稀有な感じがします。公演をやってお金をいただかないと生きていけないし、この公演は無料でいいですとは言えない。矛盾ですよね。お金にガツガツするなということと、食べていかなきゃいけないということ。そういう意味では、大竹野さんが描く犯罪者は、生きることにすごく矛盾を抱えて、結果、罪を犯します。大竹野さんは、そうした人間の生きていく矛盾と常に闘っていたんじゃないかと思うんです。
岩崎:そして寄り添うという方法もとっていらっしゃった。昔の関西の小劇場の現場って、劇場に荒くれ者がいっぱい集まって、喧嘩がよく起こったんです。それを率先して止めていたのが大竹野さん。あの人は拳を握りしめなかった。「暴力では何も解決しないですよ」と止めに入ったのが大竹野さんだった。だから、非暴力の人だったと思います。
綿貫:片や、これはよく作家が言うのですが、自分は演劇をしていなかったら犯罪者になっていたかもと。大竹野さんのエピソードのひとつで、昔、電車の中でタバコを吸っていた若者を注意して駅でボコボコにしたことがあって、そのときの記憶がないと聞きました。
岩崎:共存していたんでしょうね。
綿貫:そして、その矛盾をホンに投影していたのだと思います。彼の作品はその世界観、まなざしが優しいですよね。こんなに深いところで人間に対する観察眼を持つ作家はいないと思います。
岩崎:大竹野さんがご存命で、綿貫さんとお会いになっていたら、今、新作上演の可能性だってあるわけですよね。
綿貫:出会っていたら、やっぱり新作はお願いしていたと思います。『埒もなく汚れなく』には東京から時空を超えて大竹野さんに会いにくる東京のプロデューサーも登場します (笑)。でも、依頼しても大竹野さんは書かないって言ったと思うな。そして、それでも口説き落とすために何年も大阪に通う気がします、私。
■『山の声』のこと
 岩崎:今回、『山の声』も初演の俳優で同時上演されますね。
岩崎:今回、『山の声』も初演の俳優で同時上演されますね。
綿貫:『山の声』は大竹野さんの遺作です。ただ、この作品のモデルになった加藤文太郎さんと大竹野さんの生き様がすごくリンクするんです。もともと大竹野さんは彼のことを知らなかったんですが、編集者の小堀純さんに「加藤文太郎って知ってるか? お前と似てるよ」と薦められて知ることになります。彼も働きながら登山をしていましたし、大竹野さんと通じるところがあって、このホンを書いたんじゃないかなと思うんです。
岩崎:出演は、戎屋海老さんと遊劇体の村尾オサムさんですよね。大竹野さんは売れる気満々の役者はあまりお好きじゃなかったと記憶しています。「犬の事ム所」や「くじら企画」を観に行くと、なんて潔い人たちが出ているんだろう、カッコいいなと思った。
綿貫:カッコいいんですけど、それだけじゃなかった気もします。その部分を今回の改訂で新たに描きたいと思っています。特に35才頃に書けなくなって家を出るというエピソードも盛り込んでいます。そのあと、『海のホタル』『サヨナフ』『夜、ナク、鳥』といった事件ネタを続けざまに書くのですが、やっぱり、事件物も厳しくなっていく。それは、犯罪者がなぜそんなことをするのかを理解できないまま事件を書き続けることが、純粋な大竹野さんには苦しかったのではないでしょうか。それで山に行くんです。山登りをしていると、何も考えなくていいし、登山自体が死の恐怖と常に隣り合わせですよね。獣の気配を感じたり、足を滑らしたら転がり落ちてしまうかもしれないという恐怖を感じたり。書けなくなった時期にそういう感覚を体験することで、今までとは違う創作意欲が湧いて、『山の声』を書いたんじゃないかと思います。『山の声』の後に、実は次の構想もあったそうなので、もし生きていたら、どんな作品を書いていたのかと思うとすごく残念ですし、山が好きで海で死んだって…ほんと伝説ですよ。
岩崎:いや、大竹野さんは山が好きで山で死んじゃダメな気がします。僕からしたら、ある日突然、ひょっこりいなくなった感じがするんです。
綿貫:そういう危なっかしい人だったとも奥さんから聞きました。熱中するとそれに向かってどこまでも突っ走っていっちゃうからと心配していたそうです。
■大竹野正典没後10年企画とこれから
綿貫:二年前に奥さんに「没後10年企画をやりましょう。東京では私がやるから、大阪でもやりましょう」と声をかけたところから始まりました。コットーネでは単独の企画として、第1弾に『山の声』、第2弾に『夜が摑む』、第3弾が今回の改訂版『埒もなく汚れなく』と『山の声』オリジナル版の連続上演。そして第4弾では次世代に大竹野さんの作品を渡していく企画を考えています。
岩崎:大竹野さんへの並々ならぬ熱量はまだまだ感じます。
綿貫:『山の声』はずっと続けていくつもりです。普遍的な話なので、翻訳もして、海外にも持っていきたいです。だから次の目標は、『山の声』を持って世界に出るぞという感じですね。また、この『埒もなく汚れなく』は、私たちが考える大竹野さん像であってフィクションですが、お金優先の世知辛い今の世の中で、こういう稀有な人がいたことを演劇作品にさせてもらいました。芸術をお金に換算しないという、この純粋な生き方と生き様を見ていただきたい。そして、生きていくとはどういうことなのか、芸術をやりながら食べていくとはどういうことなのかを、もう一度考える機会になればと思います。
岩崎:若い作家のなかには、どうしたら書けますかと安直に聞き過ぎる人もいますが、この作品を観て、苦しんでみようと言いたくなりますね。
綿貫:大竹野さんは戯曲賞にも本当に興味がなかった。OMS戯曲賞やテアトロ・イン・キャビン戯曲賞も奥さんが黙って応募したらしく、「なんでそんなことするんや」と言われて、「賞金が欲しいんや。生活の足しや!」と喧嘩したと聞きました。でも、奥さんは彼の才能を信じていて、女優だけでなく制作もされて支えていた。夫婦であって演劇の同志でもあった。『埒もなく…』を立ち上げるとき、奥さんに「大竹野さんを芝居にしたいんですけどいいですか」って電話したんです。「別に構いませんけど…芝居なんかになりますかねぇ」とおっしゃったことを覚えています。なります。しました。だからこそ、この作品は、演劇をやっている人も、そうじゃない人も、そして今、演劇をやめてしまった人にも、是非みていただきたいと思っています。
2019年4月 大阪市内
オフィスコットーネプロデュース
大竹野正典没後10年記念公演 第3弾
改訂版『埒もなく汚れなく』『山の声』
2019年5月24日(金)~27日(月)
公演詳細
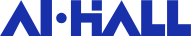




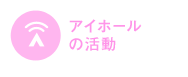


![[予約受付中]
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
令和7年度もやります!
\焼酎亭AI・HALL寄席/
関西小劇場で活躍する俳優を中心に結成された「焼酎亭一門」。
アイホールのイベントホール ホワイエに高座を設置し、カジュアルな落語会を2021年から開催しています。
役者ならではの落語。
古今東西の名曲を奏でるお囃子隊の演奏。
にぎやかで楽しいアイホール寄席へ、ぜひお気軽にお越しください
アイホール寄席初出演の方もいらっしゃいますよ~
出演者など詳細はアイホールWEBサイトまで(@ai_hall)
https://www.aihall.com/aihallyose_koi0531/
=====
焼酎亭AI・HALL寄席~鯉~
2025年5月31日(土)13:00/17:00
料金:1,000円(全席自由)
※配信チケットもございます!
[予約方法]
※いずれも当日のご精算となります。
▼予約フォーム
https://torioki.confetti-web.com/form/3952/12718
▼アイホール
TEL:072-782-2000(9:00~22:00/火曜休館)
MAIL:info@aihall.com
=====
#焼酎亭 #アイホール寄席 #鯉 #寄席 #落語会 #落語 #役者落語 #演劇 #芝居 #アイホール #伊丹市立演劇ホール #伊丹 #itami](https://www.aihall.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)